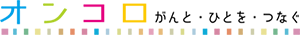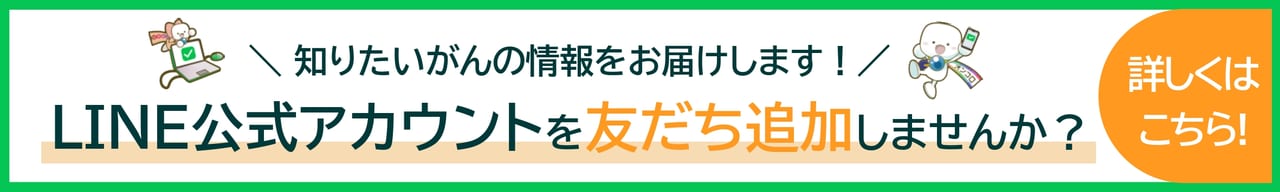がん患者の終末期の療養実態を把握するため、厚生労働省が約2万人の遺族を対象とした初の大規模調査を2017年度から始める。結果をもとに、患者が住み慣れた地域で質の高い療養を受けられるようにする対策の検討に生かす方針だ。この調査を踏まえ、「終活」について考えてみたい。
終活の二面性
雑誌で「終活」という造語が使われ始めたのは2009年。時代に合致したためだろう、あっという間に言葉が広まり、いまや終活セミナーや終活カウンセラーなど関連ビジネスは花盛り。少子高齢化や、好むと好まざるとにかかわらずあらゆることを個人が自己の責任で引き受けざるをえない「個人化」に伴う社会の変化・変容だ。
例えば、高齢の「おひとりさま」が増え、老後や死後の様々な事務を誰に託すのかを考える必要が出てきた。それは一面では、例えば葬儀のやりかたが伝統に縛られることなく、自分の意思を反映できる自由が広がるといった積極的な意味合いはある。だが一方、意識しているかどうかは別にして、家族や地域共同体が揺らぎ、「お任せ」といかなくなったために自ら動かざるをえなくなったことも否定できない。この両面性を意識していないと、終活はますます社会の個人化を進めることになりかねないと危惧している。
「迷惑をかけたくない」って…
終活にからんでよく聞く言葉に、「迷惑をかけたくない」がある。家族らに迷惑をかけない、遺される人々のための活動であるということで、終活はますます「よいこと」と肯定的にとらえられがちだ。もちろん、死後に誰に連絡すべきか、遺産をどうするかなど、決めておくことで遺された者が助かることは否定しない。大切な事務的手続きだと思う。だが、遺される人たちが本当に望んでいることばかりしているのか。じっくり考えてみたい。
例えば「本当は葬儀をしてあげたいのだけど、本人が直葬(火葬だけで葬儀はしない)にしてくれと遺言していて…」と戸惑う遺族の声も耳にする。終活が実は「迷惑をかけない自分という自分らしさ」を実現する、独りよがりになっている場合もあるのではないか。目をそむけたくなる死という現実を見据え、人生の最終盤をどう過ごし、どのように最期を迎えたいかを、家族ら近しい人たちと認識共有できているだろうか。
「迷惑をかけたくない」という言葉は、死を一人称(自分)だけでとらえ、家族ら近しい周囲の人々という二人称との関係性の視点が抜け落ちているように思えてならない。いま流行のセミナーなどで取り上げる「終活」は、二人称の人たちを煩わせまいと死を自己の領域に閉じ込め、領域内で足らざるものを埋め合わせようと、第三者から提供されるサービスを一所懸命に購入・消費しているようにみえてしまうことがある。
消費だから、「効率的か」「損か得か」の視点で捉え、精神的な深まりや死生観の成熟といった面がなおざりになりがち。終活をすることで、自己の領域をめぐる壁は高くなる。相手を慮ることが逆に個人化を深める矛盾がある。思いやりの心は美しい。だが、そもそも死は関係性、特に二人称との関係性の中でこそ捉えるべきものだろう。
縦糸と横糸
誕生時から、人は他者なしでは生きていけない。動植物などあらゆる生命を含めた他者に「迷惑」をかけ続けることでしか人は存在できない。そこまで大上段に振りかぶらなくとも、家族など近しければ近しい人々ほど迷惑をかけ合う、かけ合える存在はないことに異論はないだろう。個人化で細ったその関係性にとどめを刺すかのような「自分らしさ」「迷惑をかけたくない」終活が広がっているように思えてならないのだ。
関係性は生者同士という横糸のみならず、生者と死者という縦糸にもある。日本では「ご先祖様」という言い方で、お盆やお彼岸、仏壇に日々向き合うなど折に触れて生者と死者は交流し、人は死者の視線に包まれながら生きてきた。死者の紡いだ生命の流れの末に自分が存在することを時に意識することで、命の不思議や尊さを思う。
だが、個人化で横糸が弱まったこの「無縁社会」の中で、直葬のように死者を弔う儀礼的なものさえ否定する動きが広がるのは、生者と死者との関係を、遺された人々と自分との関係を、閉ざすことのように思える。自ら縦糸をも切る「絶縁社会」。そんな社会が生きやすい社会といえるのだろうか。死者が大切にされない社会(それは自分が死んでも大切にされないことを目の当たりにする社会だ)で、生者だけが尊重されるとは思えない。
関係性の見つめ直しこそ大切
いま必要なのは関係性を断ち切ることではなく、縦糸と横糸を紡ぎ直すことだろう。死は誰にも平等に訪れるからこそ、社会全体で、紡ぎ直したしなやかな編み目で、受け止める。自己の領域に死を囲い込むのではなく、関係性の中で死生観を成熟させながら受容していくことが重要だと考える。
がんなど病気は辛く苦しい。だが、そこに一筋の光明を見出したい。その光明こそが実は終活のあるべき「本質」なのではないか。人生最終盤をどのように過ごしたいかを考え、周囲とその思いを共有する。弱っていく過程をどう受け止め、周囲の力を借りるのか、「迷惑」をかけるのか。家族と語らう。ひとり暮らしなら、誰に自分の意思を託すのかを考える。人間関係の見つめ直しであり、再構築でもあるだろう。それはひいては医療・介護の制度問題など、社会のありようにまで広がる視点を、本人にもその周囲の人たちにも提供する。縦糸と横糸を紡ぎ直す一歩になるに違いない。
プロフィール
立教大学社会デザイン研究所研究員 星野哲(ほしの・さとし)
1962年、東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、立教大学21世紀社会デザイン研究科前期博士課程修了。朝日新聞記者として25年以上前に墓や葬儀を取材したさい、それらを通じてみえる家族のありようや社会の変化に興味を抱き、葬送から介護、医療などライフエンディングステージに関する諸問題を取材・研究している。2016年、朝日新聞社を退社してフリーに。現在、立教大学21世紀社会デザイン研究科兼任講師、NPOエンディングデザイン研究所研究員。
単著に「葬送流転 人は弔い、弔われ」(2011年、河出書房新社)、「終活難民-あなたは誰に送ってもらえますか」(2014年、平凡社)。
リサーチのお願い
<募集終了>AYA世代時にがんに罹患された患者さんとその配偶者の方へのイン…
2024.02.15
- リサーチ
<募集終了>【ご家族の方】学生時代にがん患者さんの治療・生活のサポー…
2023.11.06
- リサーチ
リサーチ(調査)結果一覧
2018.04.02
- リサーチ
オンコロリサーチについて
2018.02.16
- リサーチ