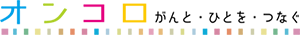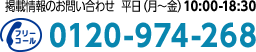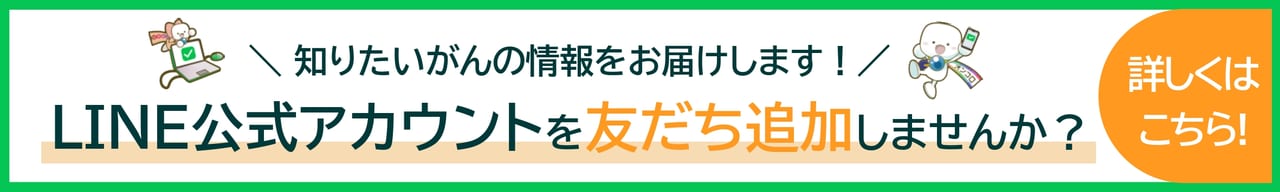目次
腎細胞がんの治療の決め方
腎臓がんは、放射線療法や殺細胞性抗がん剤に対する感受性が低いため、手術が治療の基本となります。
手術が難しい症例や、遠隔転移のある場合に対しては、全身療法として分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、サイトカイン療法が使われます。
腎細胞がんの手術
腎細胞がんでは、腎摘除術が一般的ですが、比較的早期に発見された場合には、腎部分切除術も検討されます。
また術式としては、おなかを開けて行う「開腹手術」と、おなかに小さな穴を開けて腹腔鏡を入れて行う「腹腔鏡手術(後腹膜鏡手術)」、更に腎部分切除術では「ロボット支援手術」も選択肢となっています。術式は、がんや患者さんの体調などを見て総合的に判断します。
腎部分切除術(腎機能温存手術)
がんが広がっている部分だけを切除し、残った腎臓の機能を温存する方法です。主にがんが腎臓内にとどまっており、大きさが比較的小さい(4cm以下)の場合に適応となりますが、がんの位置などによっては部分切除が難しい場合もあります。
腎摘除術(根治的腎摘除術)
がんが生じている側の腎臓をすべて切除する方法です。腎部分切除術ではがんを取り切ることが難しい場合に選択肢となります。がんの位置や副腎への転移の状況によって、腎臓の頭側にある副腎まで切除するかどうかを判断します。また、がんの広がり方によっては、腎臓だけでなく、周囲の臓器や血管内にあるがんを併せて切除することもあります(静脈内腫瘍塞栓摘除術)。
腎摘除術は、片側の腎臓をすべて取り除くことになりますが、もう片方の腎臓が正常に働いていれば、ほとんど生活に支障を来すことはありません。
手術による合併症として、縫い合わせた部分から出血を起こすことがあり、動脈塞栓術、または開腹による再度の縫い合わせにより対処します。また、尿漏れが起きることもあり、カテーテルによって様子を見ますが、回復しないようであれば腎摘除術を検討することになります。
腎細胞がんの凍結療法
体外からがんに針を刺し、超音波検査や画像検査で確認しながらアルゴンガスでがん組織を凍結させ死滅させる方法です。がんが小さい場合の局所治療のひとつで、高齢者や合併症のある場合、あるいは手術を希望しない場合に選択肢となります。
腎細胞がんのラジオ波焼灼術(RFA)
腎臓がんのある場所に皮膚表面から電極を刺入し、高周波電流で腫瘍組織を焼灼凝固する治療です。腫瘍径が4cm以下の腎臓がんを小径腎がんと呼ばれ、小径腎がんの中でも1~3cm以下で、転移や脈管侵襲のない腎臓がんでは、RFAが良い適応とされています。一方、2011年に凍結療法が保険収載となってからは、凍結療法が施行される割合が高くなっています。
腎細胞がんの薬物療法
薬物療法は、手術のみではがんを取り除くことができない場合に選択されます。
分子標的薬
がん細胞の増殖に必要な特定のタンパク質を標的として、選択的にがんの増殖を抑える働きがあります。腎細胞がんでは二種類の薬が使われます。
ひとつはチロシンキナーゼ阻害剤で、増殖に必要なシグナルを伝えるタンパク質の働きを抑制します。もうひとつはmTOR阻害剤で、がん細胞に栄養を届けるために作られた異常な血管生成を抑える働きがあります。
サイトカイン療法
サイトカインとは、免疫細胞が分泌するタンパク質の総称で、全身に作用することによって免疫の活性化を助ける働きを持ちます。腎細胞がんでは、インターフェロンα(IFN-α)やインターロイキン2(IL-2)が使われます。
副作用としては、発熱や倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐おうと、頭痛、脱毛、白血球減少などが報告されています。
免疫チェックポイント阻害剤
がん細胞は、免疫細胞からの攻撃から逃れるために、免疫細胞の働きにブレーキをかけることがあります。このブレーキを解除し、免疫細胞の作用を回復させて、がんへの攻撃力を高める働きをするのが免疫チェックポイント阻害剤です。標的とする分子によって種類がことなっており、腎細胞がんでは抗PD-1抗体、PD-L1抗体CTLA-4抗体の3種類、計4剤が適応となっています。
| 主な腎臓がん(腎細胞がん)治療薬 | 一般名 | 製品名 | |
| 分子標的薬 | チロシンキナーゼ阻害剤 | スニチニブ | スーテント |
| ソラフェニブ | ネクサバール | ||
| パゾパニブ | ヴォトリエント | ||
| アキシチニブ | インライタ | ||
| カボザンチニブ | カボメティクス | ||
| mTOR阻害剤 | テムシロリムス | トーリセル | |
| エベロリムス | アフィニトール | ||
| 免疫チェックポイント阻害剤 | 抗PD-1抗体 | ペムブロリズマブ | キイトルーダ |
| ニボルマブ | オプジーボ | ||
| 抗PD-L1抗体 | アベルマブ | バベンチオ | |
| 抗CTLA-4抗体 | イピリムマブ | ヤーボイ | |
| サイトカイン | IFN-α | ||
| IL-2 | |||
一次治療で使う薬の種類は、組織型とリスク分類に基づいて判断されます。
淡明細胞がんでは、分子標的薬に加えて免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の併用療法が選択肢となります。一方で、その他の組織型に関しては明確なエビデンスがなく、分子標的薬が第一選択薬となっています。
二次治療以降は、がんや患者さんの全身状態、一次治療で使った薬の種類に基づいて検討していきます。