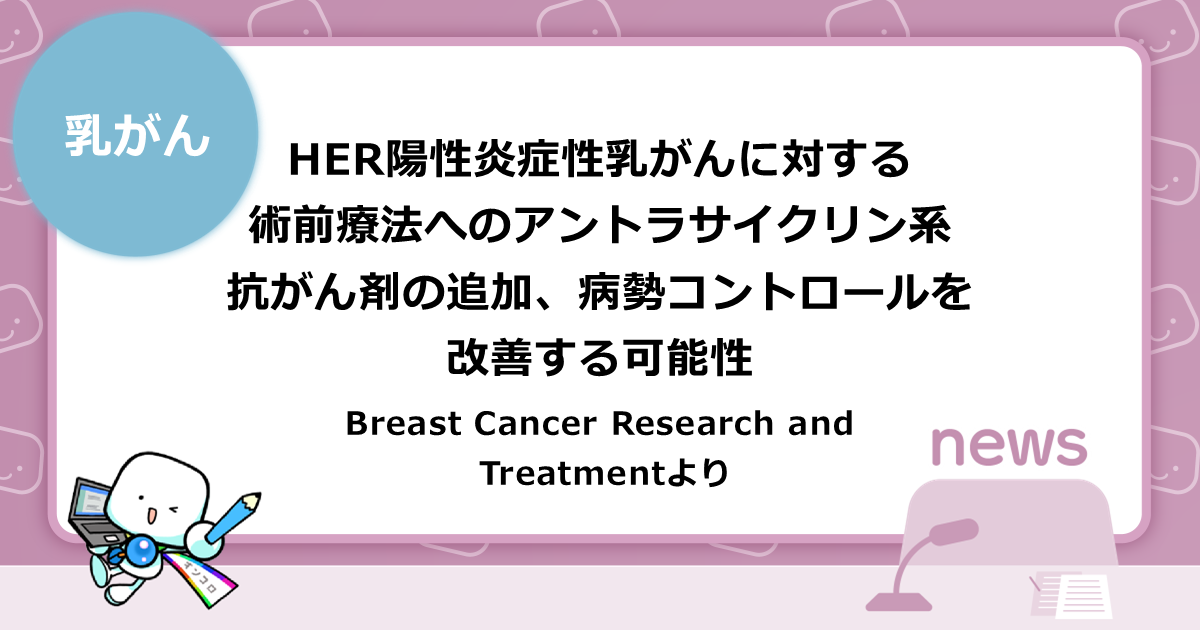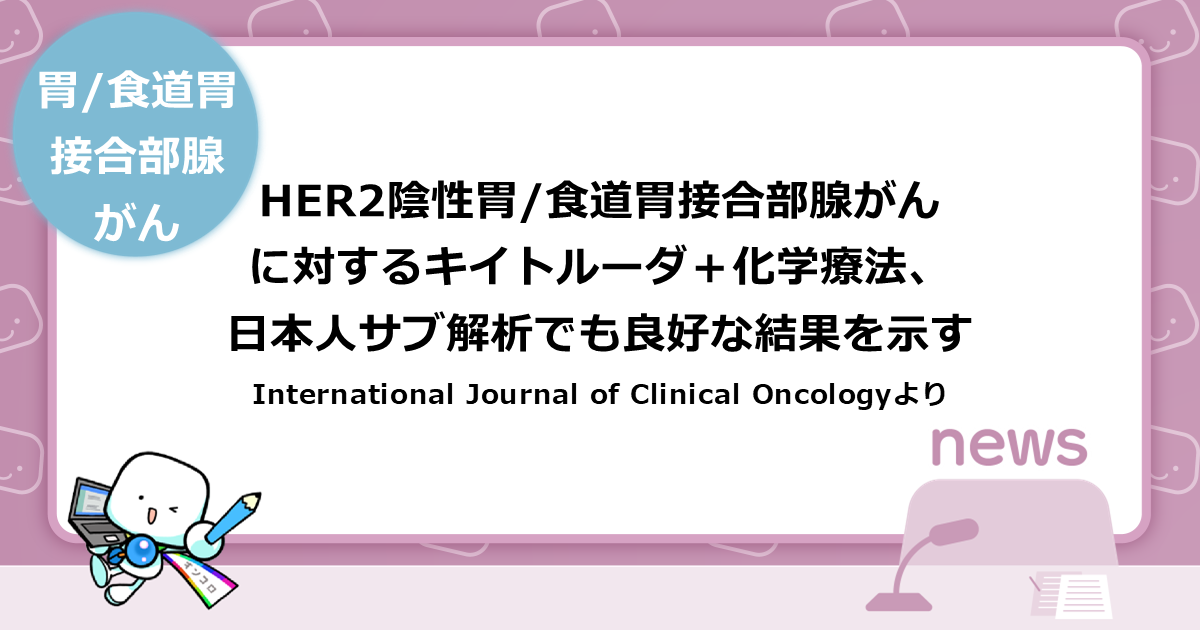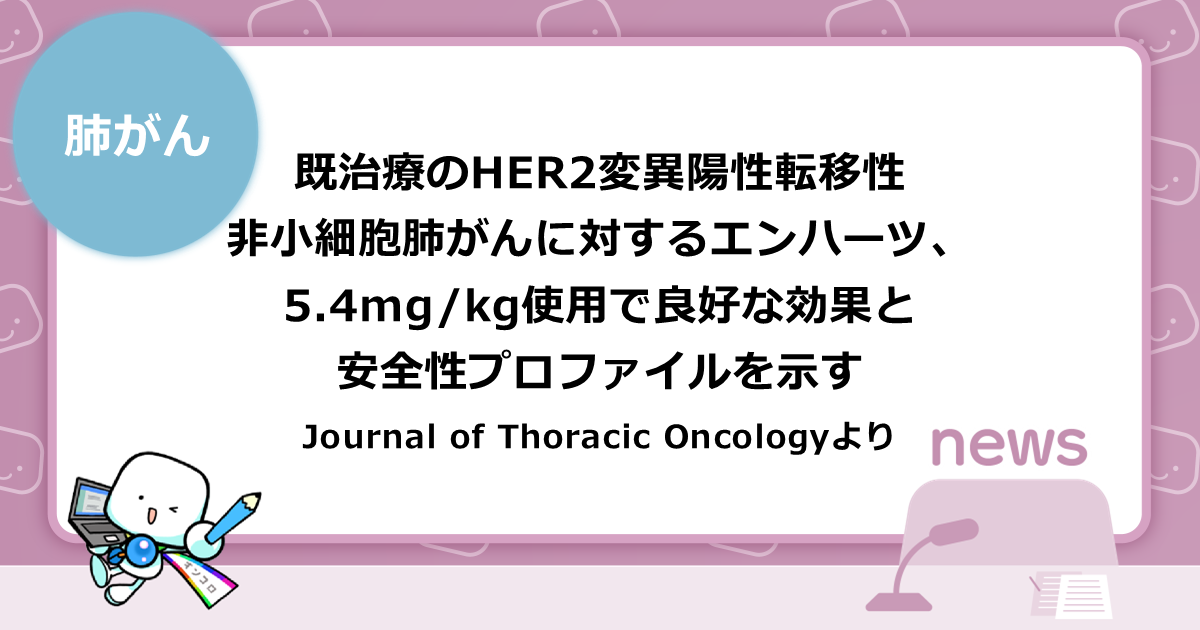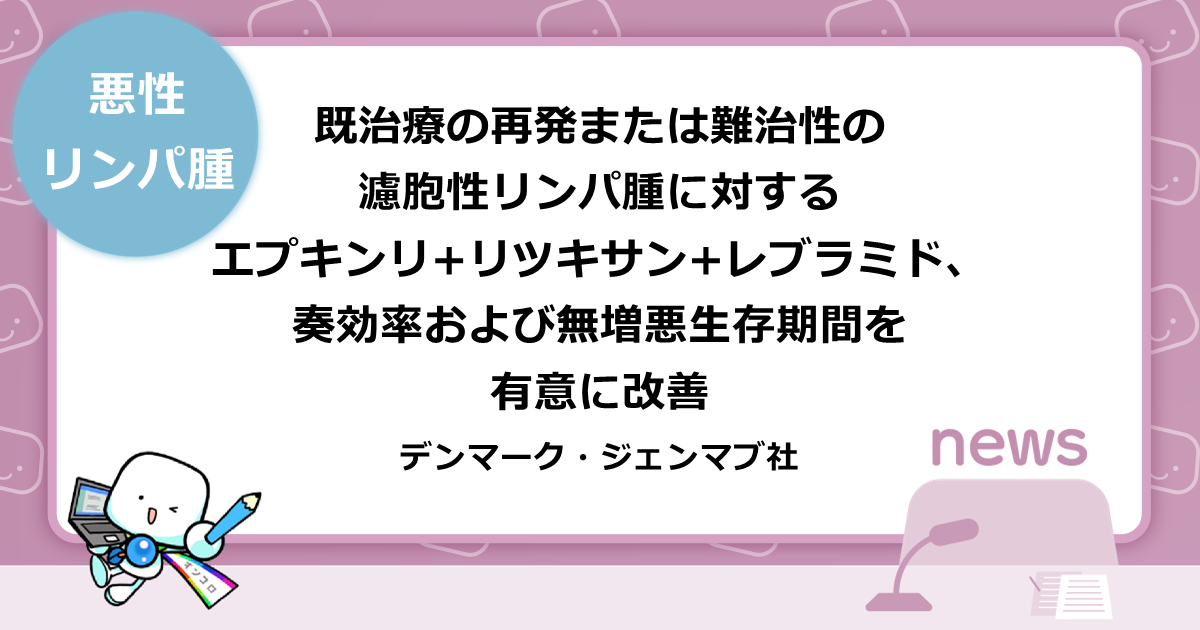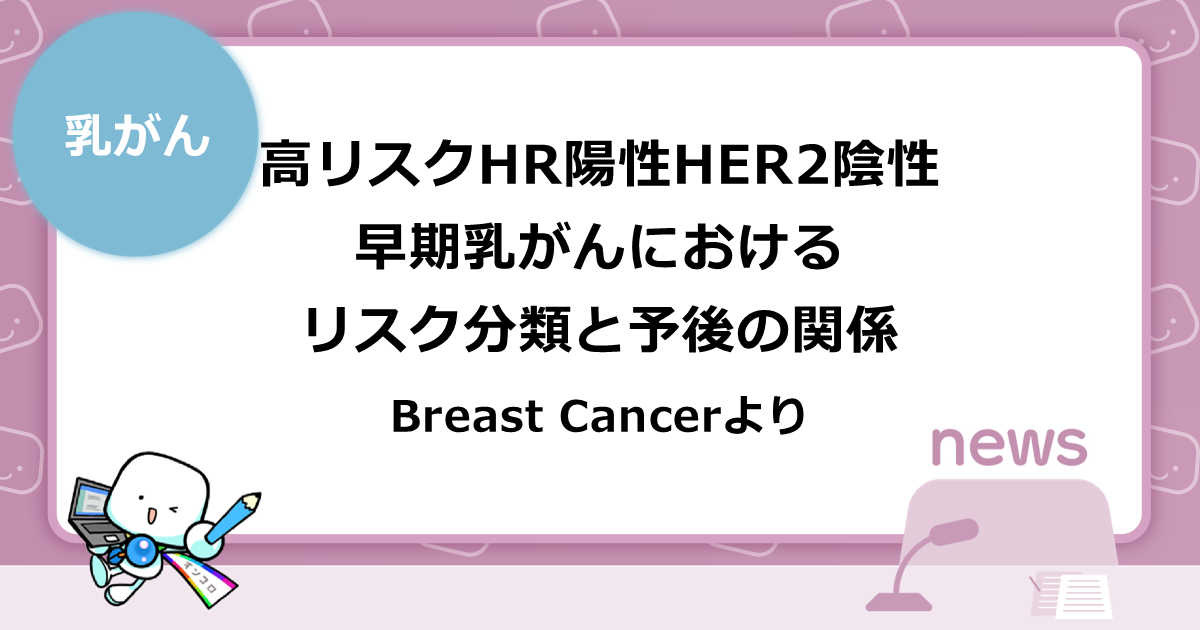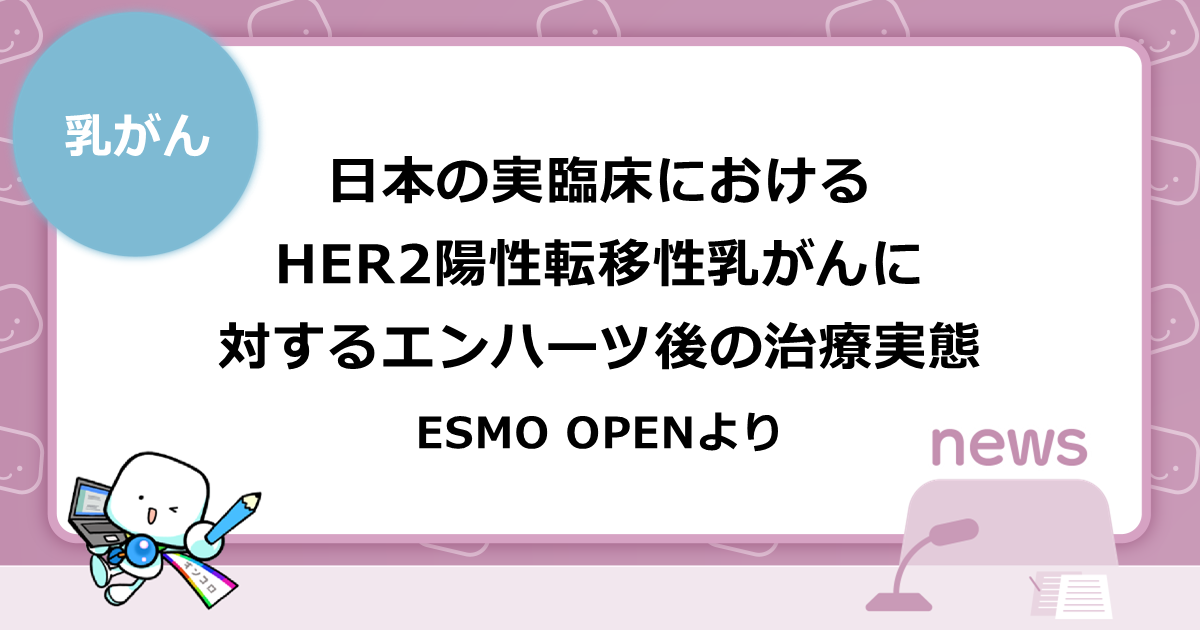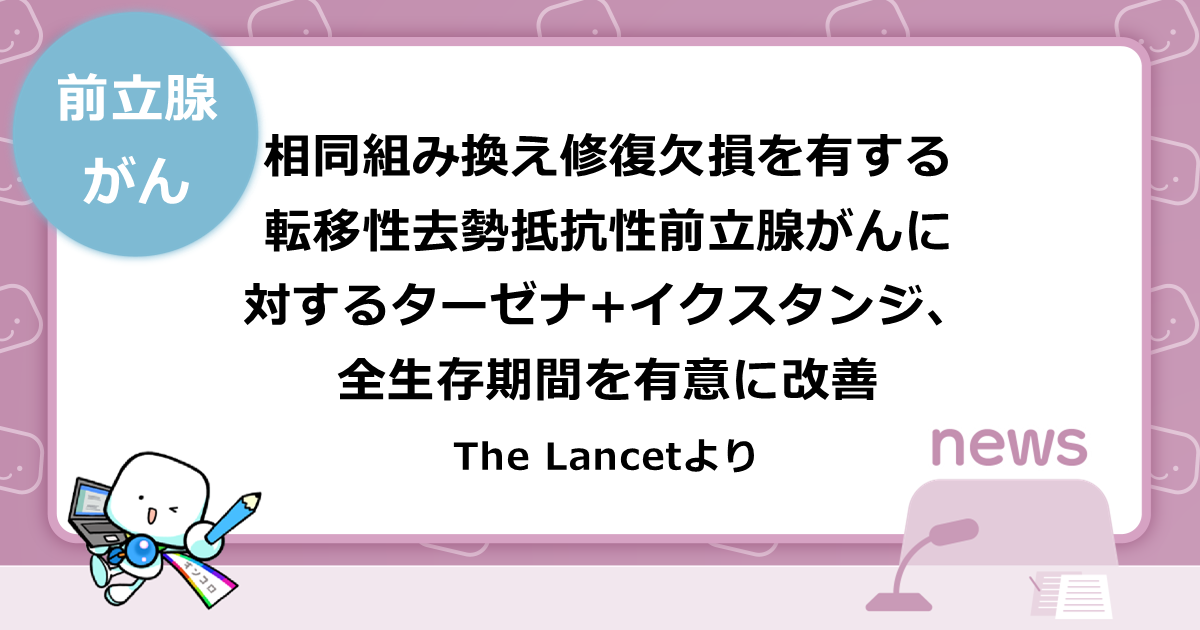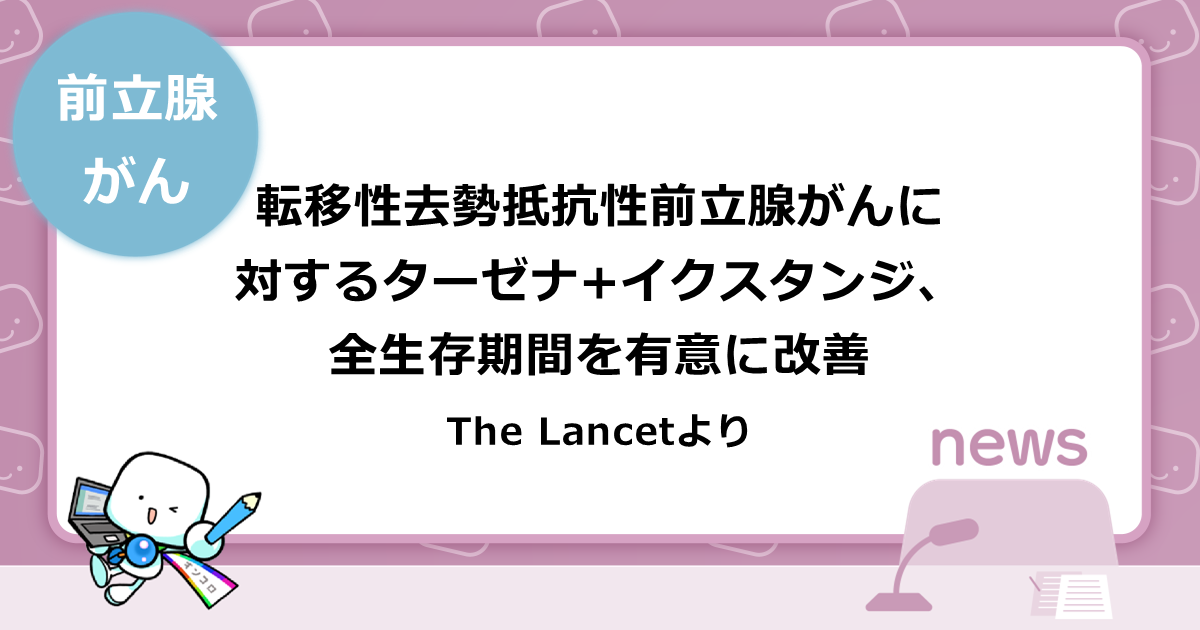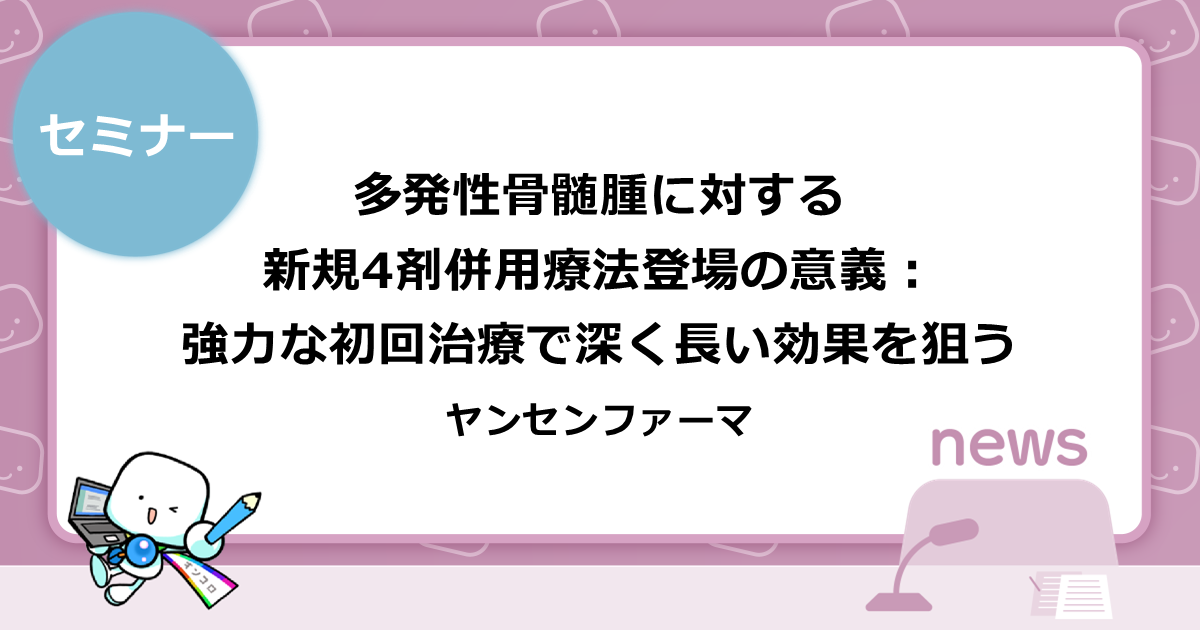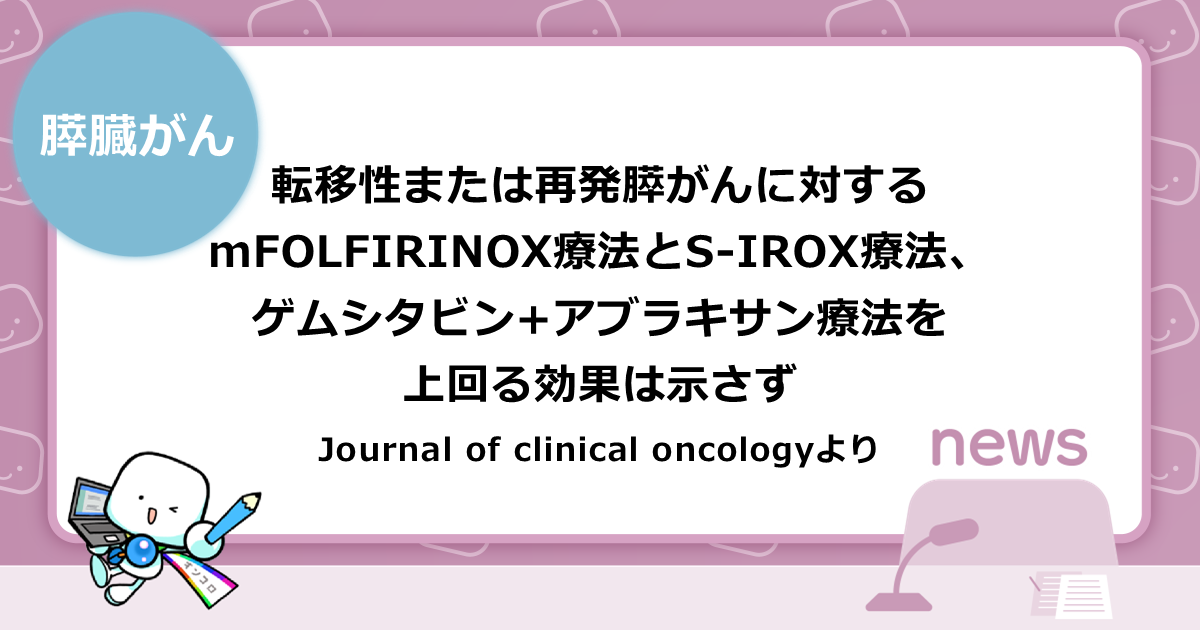目次
アジア初 インターネットを介したがんQOL研究始動
このような機運において、日本のがん医療におけるIoT導入は遅れがちであることは明白である。 そのような中、7月27日から7月29日に開催された日本臨床腫瘍学会にて、転移性乳がん患者におけるComputer-based Health Evaluation System (CHES;チェス)を用いたQOL(生活の質)評価の有用性を検討するパイロット研究(UMIN000023250)結果が、神戸市立医療センター中央市民病院の木川 雄一郎氏によって発表された。 ここでいうComputer-based Health Evaluation System (CHES)とは、EORTCというヨーロッパを拠点としてがん治療や臨床研究を実施する組織が提唱し、そのシステムバリデーションを構築したパーソナルコンピューター(PC)ベースの健康評価プラットフォーム(システム)となる。 EORTCはQLQ-C30など数多くのQOL調査票を開発している。すべての調査票は英語で開発されるが、日本語対応として言語検証(linguistic validation*)されたものも数多くリリースされている。しかしながら、いずれも紙ベースでの調査票であった。ゆえに、今回、日本語用として開発されたCHESは、アジアで初めての電子患者日誌(ePRO)となる。 *言語検証(linguistic validation):単に、英語を日本語に翻訳しても、実診療に即していない翻訳となる場合が多々ある。そうなると、本来取得したい回答が得られないことがあるため、翻訳が的を得ているかを検証する必要がある。この検証過程を、言語検証(linguistic validation)といい、実際に一定数の患者に意見聴取を行うことが多い。まずは患者が継続使用できるかが初めの一歩 ~少しずつ進むIoT研究~
そもそもQOL評価を患者から取得する意義は、医療者評価と患者の主観評価に乖離があるからである。しかしながら、現状のQOL評価の取得は患者の通院時に限られており、医師からすると通院時以外のQOLについてはブラックボックスに包まれている。そういった意味で、電子患者日誌(ePRO)を用いて定期的にQOLを入力し、それを遠隔でトラッキングする意義はある可能性がある。事実、上述通り、仕組みは違えど米国や欧州では生存期間を延長するケースも報告された。 さて、電子患者日誌(ePRO)を研究や臨床に活用するにはどういったことが必要であろうか? 「生存が伸びた」「QOLが改善した」といった最終結果は勿論であるが、その最終結果を得るために臨床試験を行う必要があり、さらに臨床試験を行うためには、2つのバリデーション(検証)が必要がある。 1つは、システムバリデーション。これは、文字通りシステムが正常に動作するかの検証作業である。 もう1つは、患者が一定の割合以上で使用するかのバリデーション(検証)である。 今回、木川氏らが発表した研究は、まさに「バリデーションスタディ」となり、研究目的は「転移乳癌患者を対象とし、長期にわたるHRQOL(QOLと同義)を電子媒体で、高いコンプライアンス(実施率)を保ちながら施行できることを確認する」とされている。 要するに、「転移性乳がん患者にCHESを使用してもらい、長い間継続的に使用し続けることができるか?」を検証したのだ。 参加したのは、神戸市立医療センター中央市民病院に通院する16名の転移性乳がん患者。勿論、携帯型タブレット端末もしくはPCを所有しており、自身にて操作可能な患者に限られた。 これらの患者に、CHESの入力手法をトレーニングを実施、その後3か月間毎週CHESによりEORTC QLQ-C30(30問のQOL質問票)を入力を依頼した。16名の患者の年齢は38歳~70歳。年齢の中央値は58歳であり、1名は家族が代わりに入力したとのこと。なお、通院時などにCHESの入力を促すことはしなかったとのこと。 肝心な3か月間の入力順守率の中央値は84.6%であり、もともと検討していた基準をクリアし、データ収集のためのバリデーション(検証)は立証されたといえる。 しかしながら、16人中8人は入力順守率が8割以上であるが、残りの8人は入力の順守率が8割を切った。順守率が悪かったか理由は、入力忘れ3人、病状悪化4人、デバイスの不具合が1人であったとであり、さらなる改善が求められる。 一方、CHES使用期間中に一定以上QOLが低下した患者(Minimally Important Difference;MID)は50%であり、一定以上QOL低下するまでの期間の中央値は30日であったとのこと。(今回の試験の目的はあくまでもバリデーションであり、患者はQOLを入力するが医師側は介入していないことに注意)日本のがん医療へのIoT導入の基盤となるデータの蓄積を目指し。
木川氏は次のように語る。以前からePROに興味を持っていて、何とか院内に導入したいと思っていました。当初はアプリ開発なども考えましたが、そのような知識や資金もないため当然実現するわけもなく、悶々としていた時に、EORTCのホームページからこのCHESというプラットフォームの存在を知りました。そして、EORTCに問い合わせのメールを送信したのがちょうど2年前でした。それから、何回もメールでやりとりし、スカイプでのカンファレンスも数回行った後に、やっと導入することができました。 本当はBasch先生らが今年のASCOで発表したような研究(上述)を早く行って、日常臨床で当たり前に使えるようにしたいのですが、まずは日本人の患者さんできちんとシステムが機能することを確かめないといけません。そのために、今回のパイロット研究を計画しました。今後はがん種や症例数を増やして、次の段階の研究を行いたいと思っています。ただし、私はIoTを使った患者モニタリングが生存期間の延長にまで寄与するとは考えていません。アメリカと日本では医療事情が全く異なりますし、現状のマンパワーでは十分な介入を行うことができないからです。しかしながら、このようなツールが医師-患者関係の向上につながり、がん患者さんのQOL維持に貢献することは間違いないと信じています。 おそらく、将来的には老若男女を問わず、日本でほとんどの方は、何らかの形でインターネットに簡単にアクセスできる環境をもっているはずです。ITががん医療にとって当たり前の時代になるための、基盤となるデータを蓄積していければと考えています。 そしてもちろん、これらはあくまで補助ツールであって、face to faceの心のこもった医師-患者コミュニケーションが、いつの時代においても最も大事であるということを最後に付け加えておきます。まさに、木川氏は正面から日本のがん医療のIoT臨床研究のパイオニアの一人であると言えよう。








 病院の詳細検索
病院の詳細検索
 マイページ
マイページ
 オンコロとは
オンコロとは
 メディカル・サポーター
メディカル・サポーター
 Remember Girl’s Power!!
Remember Girl’s Power!!
 0120-974-268
0120-974-268