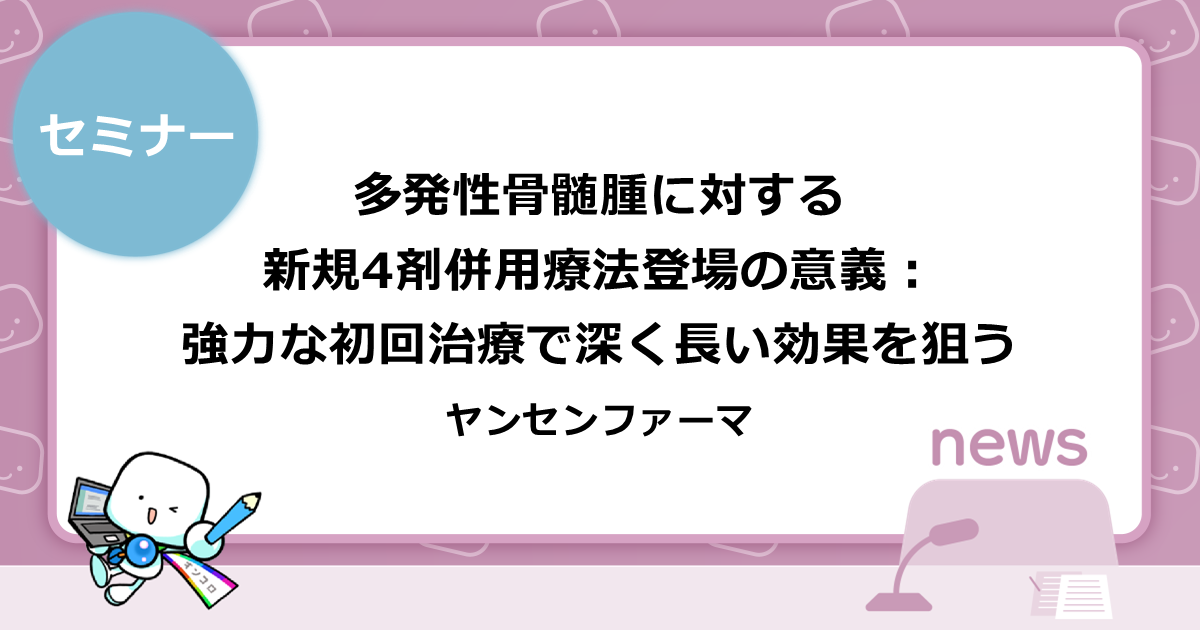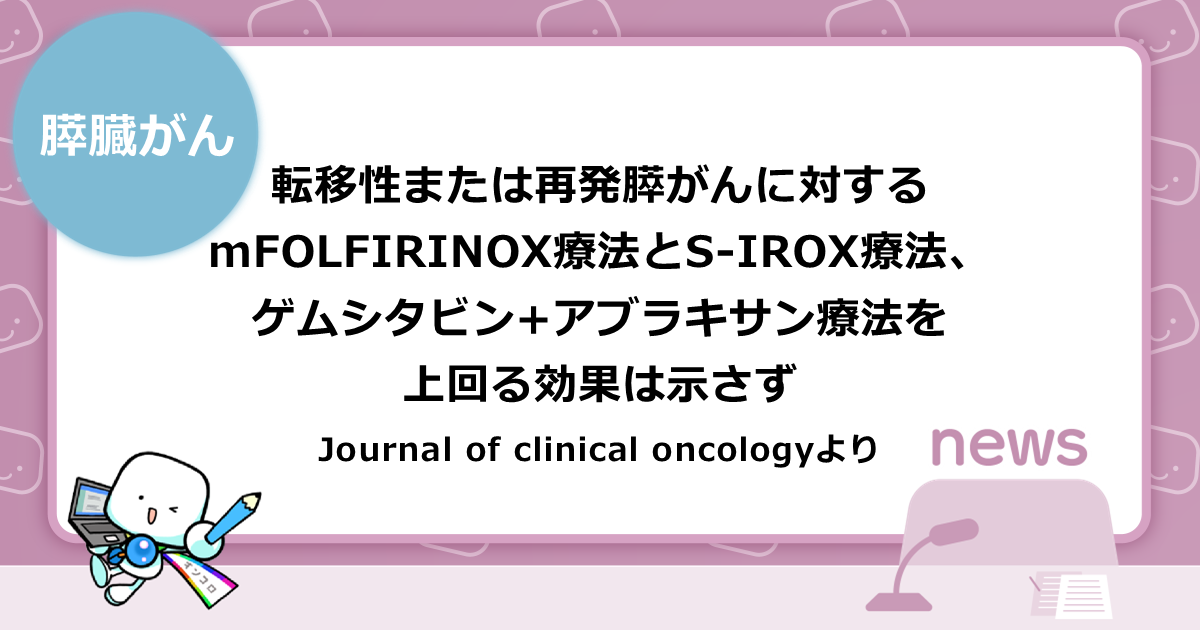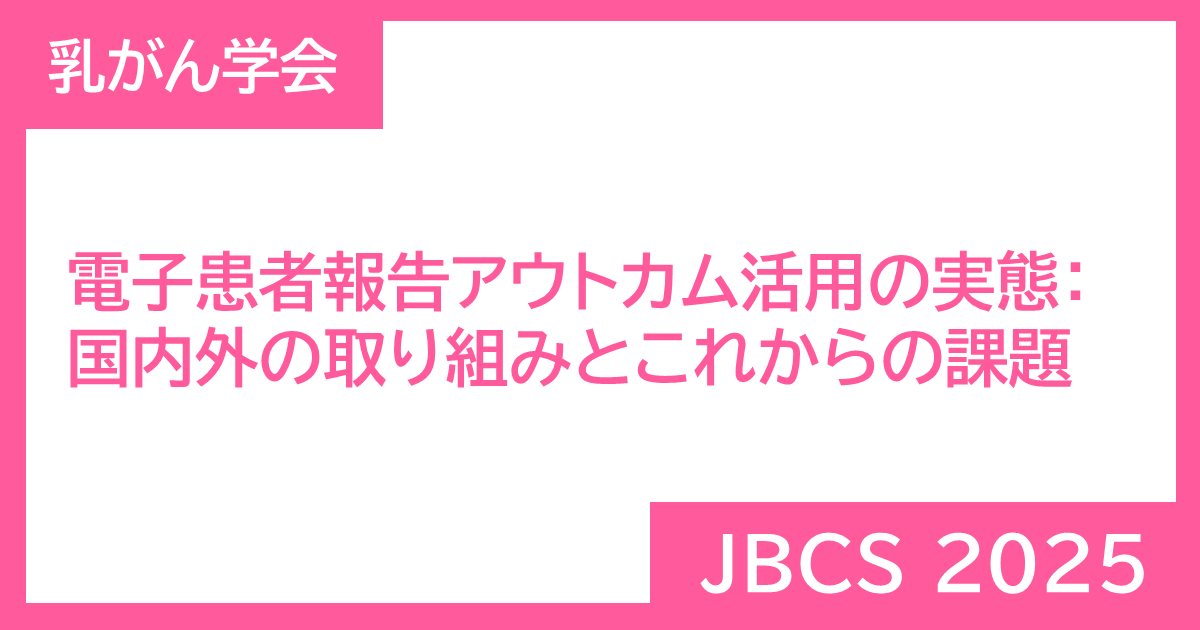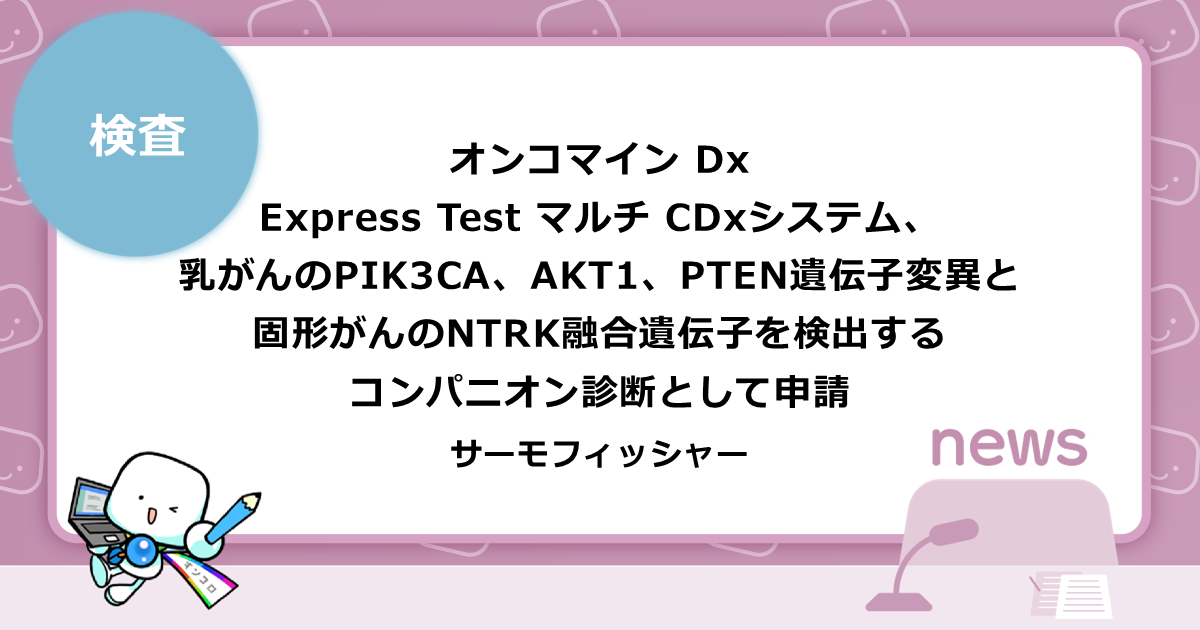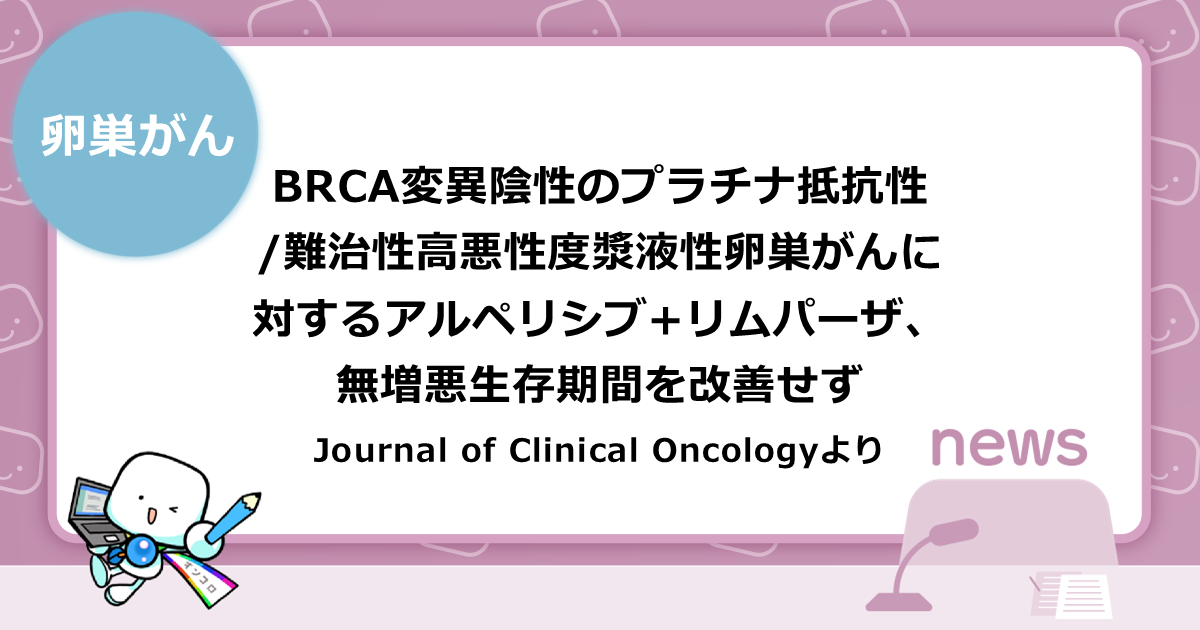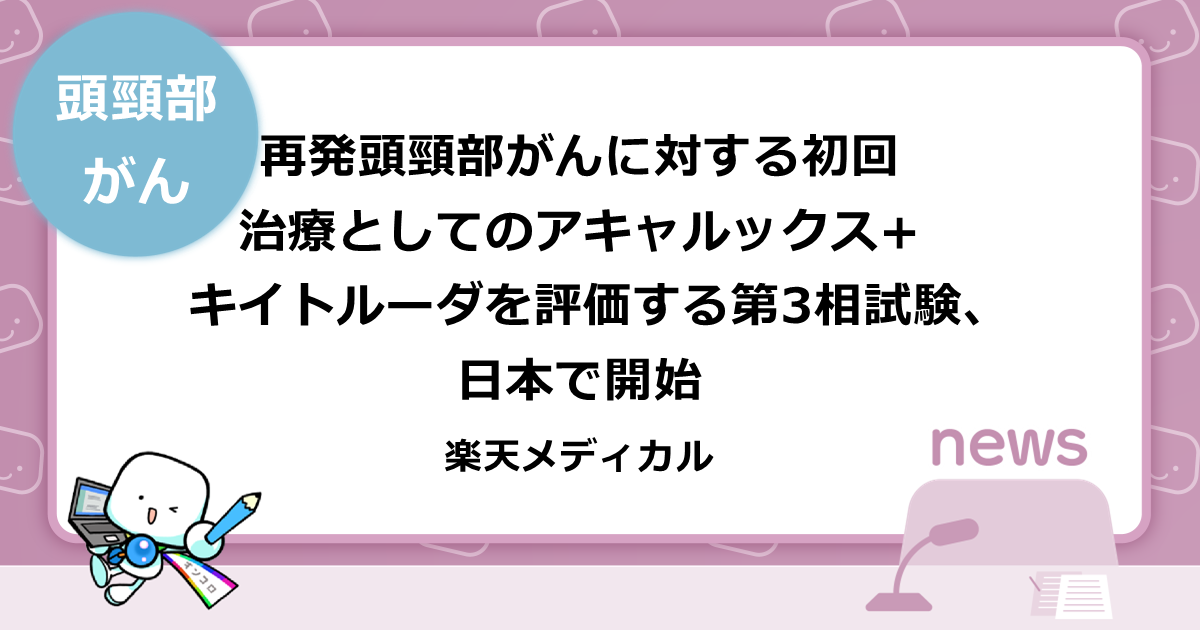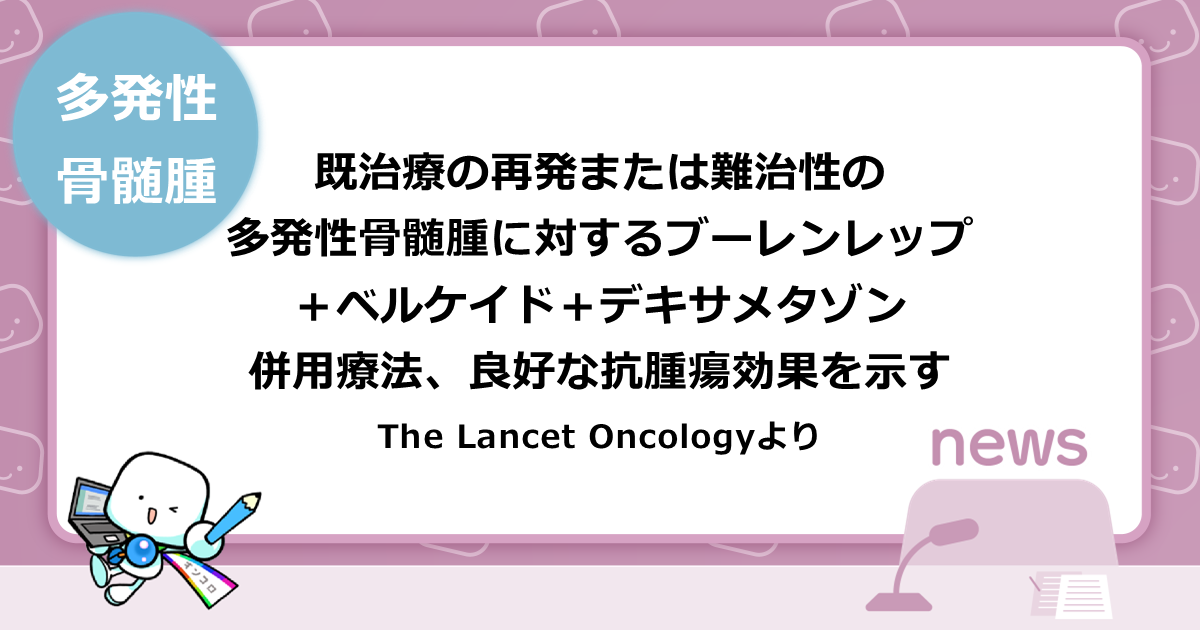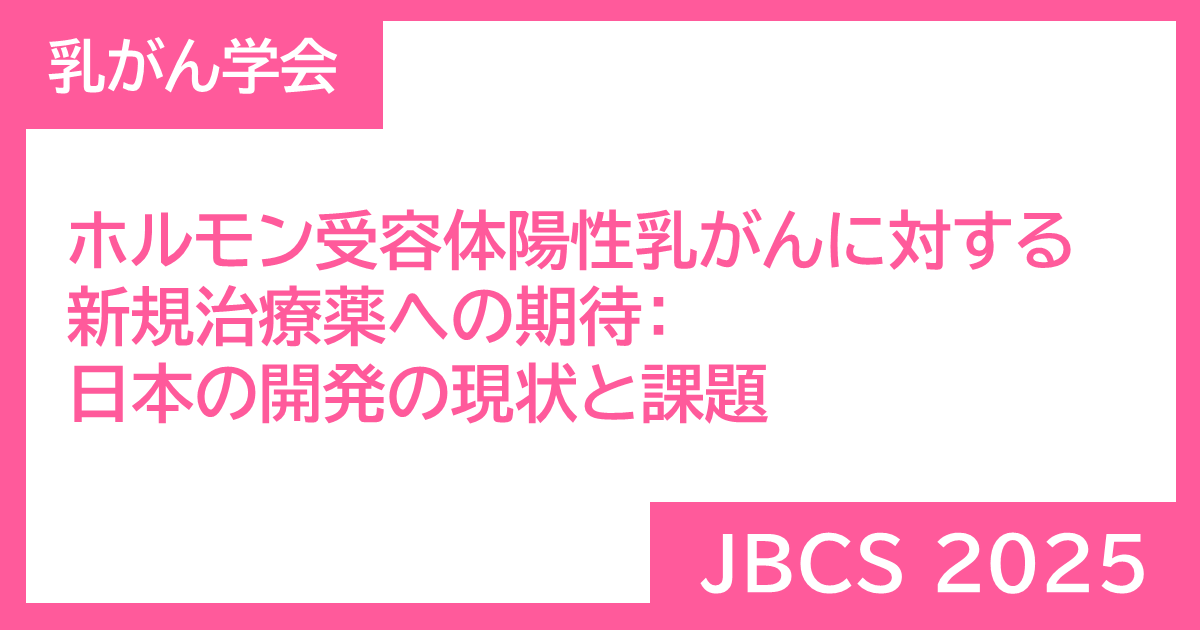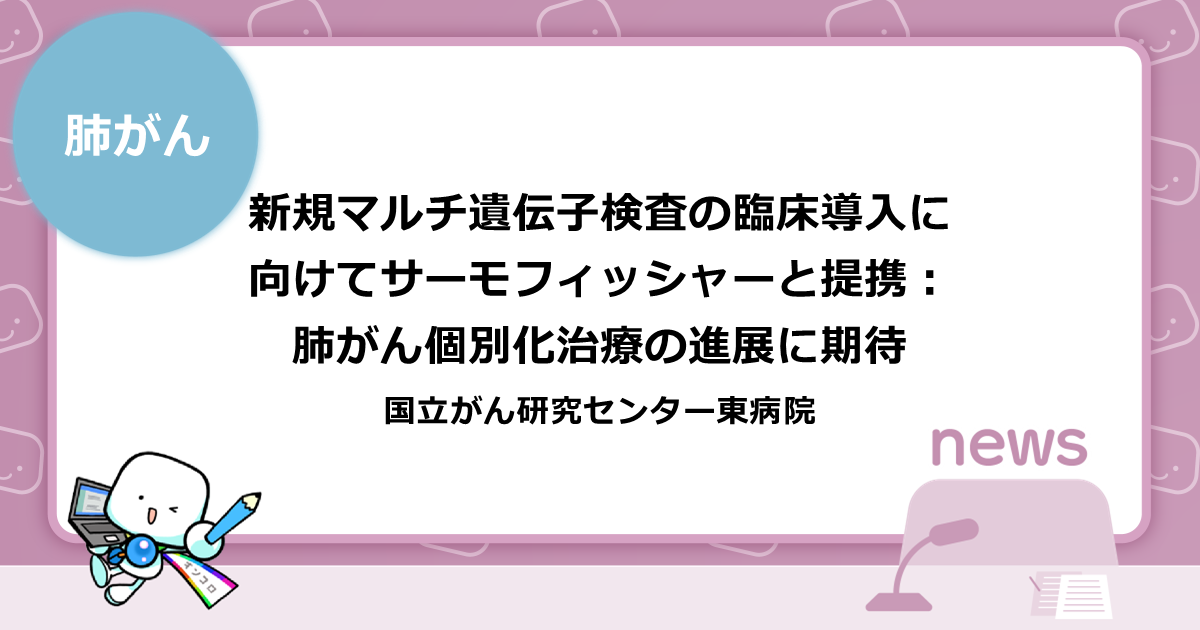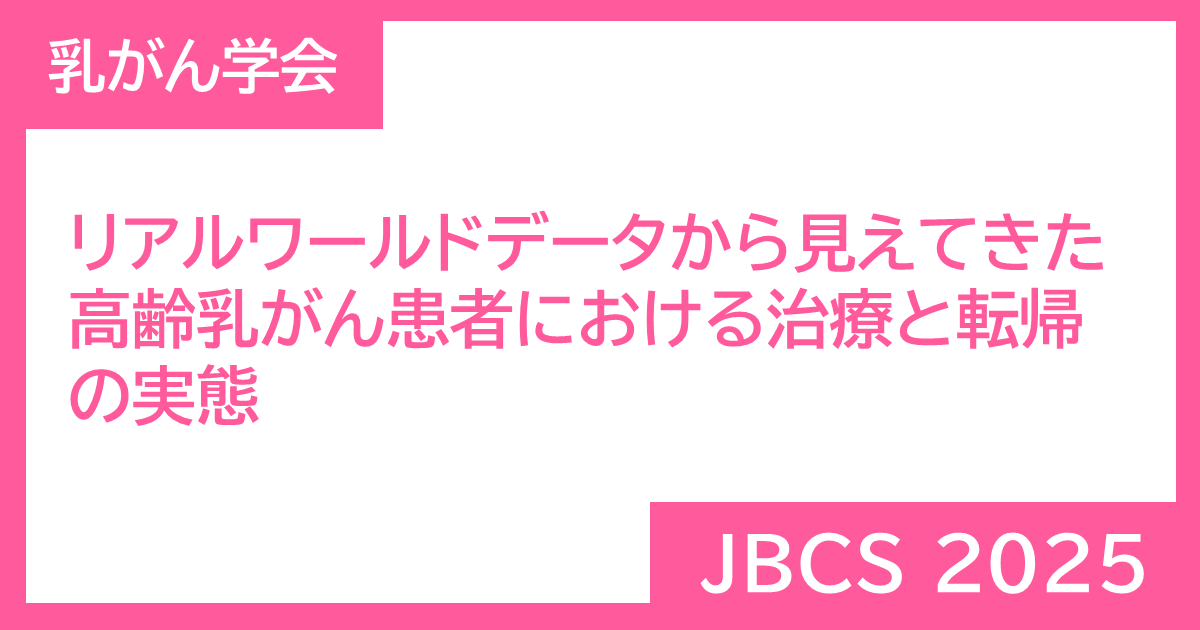2023年9月29日、株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(以下GHC)にて会場開催・オンライン配信のハイブリッド形式によるセミナーが開催された。
このセミナーは2023年8月21日に公開された白書「非小細胞肺癌患者におけるドライバー遺伝子検査実態調査 ―全国200病院のDPCデータ予備的解析結果―」について、作成にかかわった医師、患者、データ分析者にて100分にわたる講義とディスカッションが行われた。
白書の公開に関するオンコロの記事はコチラ。
開会挨拶

開会挨拶として主催者であるGHC会長のアキよしかわ氏による挨拶があった。
アキ氏自身も、複数回のがんを経験している立場であり、今回の調査のきっかけとなった肺がん患者の長谷川氏のことは以前から知っており、患者としての力を患者としての力を貰ったという。
GHCは、DPCのデータをベースとした約1,000病院データにより、日本で最大規模の急性期病院に特化したコンサルティングを実施しているとのこと。
日本の病院における医療の質のばらつきに着目し、がん医療の均てん化に向けたがん医療の質向上の取り組みもしており、本調査の実施理由との親和性が高かったようだ。
調査実施の背景説明

一般社団法人アライアンス・フォー・ラング・キャンサー(以下A4LC)代表の長谷川 一男氏からは、調査実施のきっかけについて話しがあった。
非小細胞肺がんにおいて、近年急速に新しい分子標的薬が承認されており、対応するお薬がある遺伝子変異の数は現在9種類となっているが、果たして肺がん患者がその恩恵を授かることができているのか。仮説として「肺がん患者において治療(分子標的薬)の機会に差異があるのではないか」と考えたとのことであった。
過去に、肺がん患者へのアンケートを実施したが、すべての遺伝子検査について調べていない方がほとんどであり、その実態が気になったという。
実施結果報告

GHCアソシエイトマネジャーの榎本有祐氏からは、分析方法と分析結果についての説明があった。
遺伝子変異の検査として、オンコマイン・Amoy等のコンパニオン診断が普及したことで、全国的な検査実施項目数が増加傾向となった。一方で、オンコマイン・Amoyの上市前に診断を受けた患者には、最新の検査や治療薬に関する情報が届いてない可能性があるため、患者自身へ最新情報が届けられ、自身の意思決定に基づいた医療サービスが受けられることが益々重要になってくるだろうと分析を実施してみての総括を述べた。
※本調査の結果については、すでに白書としてデータが公開されているので、結果の内容についてはコチラよりご確認をお願いします。
ディスカッション

調査の結果に対する感想から見えてきた課題、今後の展望について、白熱した議論が展開された。
すでに登壇した長谷川氏、榎本氏に加わり、肺がん医療の専門家である近畿大学 病院がんセンター長の中川和彦先生、神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器内科医長の池田慧先生が参加した。
※ここからは各テーマに沿ったパネリストの発言の抜粋を記載します。
・結果について
 ※参考:遺伝子検査項目数の推移データ[/caption]
※参考:遺伝子検査項目数の推移データ[/caption]
中川先生:Amoy検査の承認に伴い、近年多数項目での検査が増えていると感じた。過去の背景として、検査の精度の問題などでマルチの検査でうまくいかなかったということもあったが、検査の精度が向上していることも大きい。
池田先生:個人としてはポジティブな結果が見られたと感じている。ただ、3割が検査を実施していないなど課題もある。
長谷川氏:マルチの検査が思ったよりも広まっているということがわかり、まずは安心した。
・3割が実施していないことについて
池田先生:検査によるメリットを感じられないケースが存在していること。あと、十分な検査のための検体がないなどで、検査をしたくてもできないこともある。
中川先生:肺がんは高齢の患者が多いということもある。高齢の場合には治療に耐えられない状況と判断するケースもある。
ただし、分子標的薬は殺細胞性の抗がん剤よりも高齢でも使いやすい治療薬なので、今後はもっと普及させてもよいものであると感じる。
・現場での検査の選び方について
池田先生:現在はマルチをメインで使用する。
Amoyかオンコマインかについては、検査結果がわかる速さに違いがあったり、検体の状態で判断されたりする。
がん細胞の量が少ないなど検体として不十分な場合にはマルチ検査が難しい場合があり、検体をとることにも技術や工夫が求められる。
・がん遺伝子パネル検査(CGP)について
池田氏:初回で遺伝子を調べ切れていないような方に使うことができる。ただ、肺がんの場合にはすでに多くの遺伝子ががん遺伝子検査で調べることができるということもあり、使用率は高くない。また、CGPは受けることができる病院が限られているという問題もある。
・コンパニオン診断として承認されていない遺伝子変異があることが判明した場合はどうするか
池田先生:コンパニオン診断をするために認められた方法で再度検査をする必要がある。
・コンパニオン診断として認められていないことがあるのはなぜか。
中川先生:臨床試験によりコンパニオン診断として承認をとる必要があるのだが、そのためにはとても時間がかかるため。
・過去に1~3種類しか遺伝子を調べていない人がいることについてどう思うか。
長谷川氏:患者としては、お薬が承認されたら使えるようになるものであると、感じてしまう。ただし、先生方の話からもわかるが、現場で使えるように浸透していくには時間がかかるものであると思った。最先端がゆえに仕方がないものであると理解した。
3種類の検査を受けられた方が、残りの6種類を受けたいと思えば受けようとすることはできる。現在もご存命であるならば、この検査を受ける決断をするのは患者自身であるのではと思っている。
池田先生:ご存命の方には、その機会を提供することも医療者側も考えていく必要があるのだろうと長谷川さんの意見を聞いて感じた。再度検査をする場合に検体をどのように入手するか、入手できるかなどの課題はあると思う。
中川先生:1~2年前に検査を受けた方が、再度検査を受けるにあたり、新たな検体をとる方がよい。理由としては、過去に検査を受けてから現在までに受けた治療の影響や、その当時の検体の取り方が最良とは限らないためである。検査を再度受けられる状態であればそれはチャレンジしていくべきだと思う。
・総括の一言
池田先生:ポジティブな結果と感じたものの、施設間での格差があるなど、医療者側にも課題もあると感じた。患者さんが取り残されないようにしていきたいと思う。
中川先生:マルチの遺伝子検査が普及している傾向になっていることは確実である。課題としては、個々の病院ごとに見たときの状況をもっと深堀して見ていくことが重要であると感じた。
長谷川氏:A4LCとして、さらに遺伝子検査が普及していくように活動していきたいと思う。患者の立場としては、患者個人がしっかり検査を受ける判断をしていくべきだと感じた。
榎本氏:ビッグデータをもっている会社として、今回のように調査を実施し、世の中に発信していくことが重要であると思う。今回のように議論のスタート地点として可視化をしていきたいと思う。
関連リンク
非小細胞肺癌患者におけるドライバー遺伝子検査実態調査 ダウンロードページ
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン ウェブサイト
一般社団法人アライアンス・フォー・ラング・キャンサー ウェブサイト








 病院の詳細検索
病院の詳細検索
 マイページ
マイページ
 オンコロとは
オンコロとは
 メディカル・サポーター
メディカル・サポーター
 Remember Girl’s Power!!
Remember Girl’s Power!!
 0120-974-268
0120-974-268