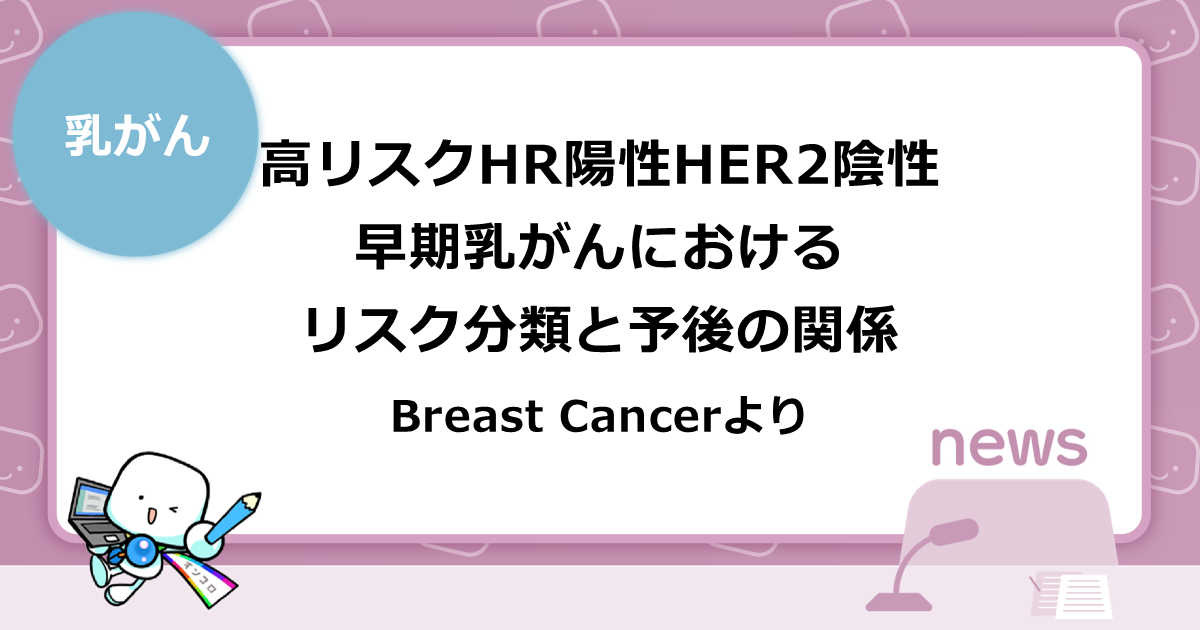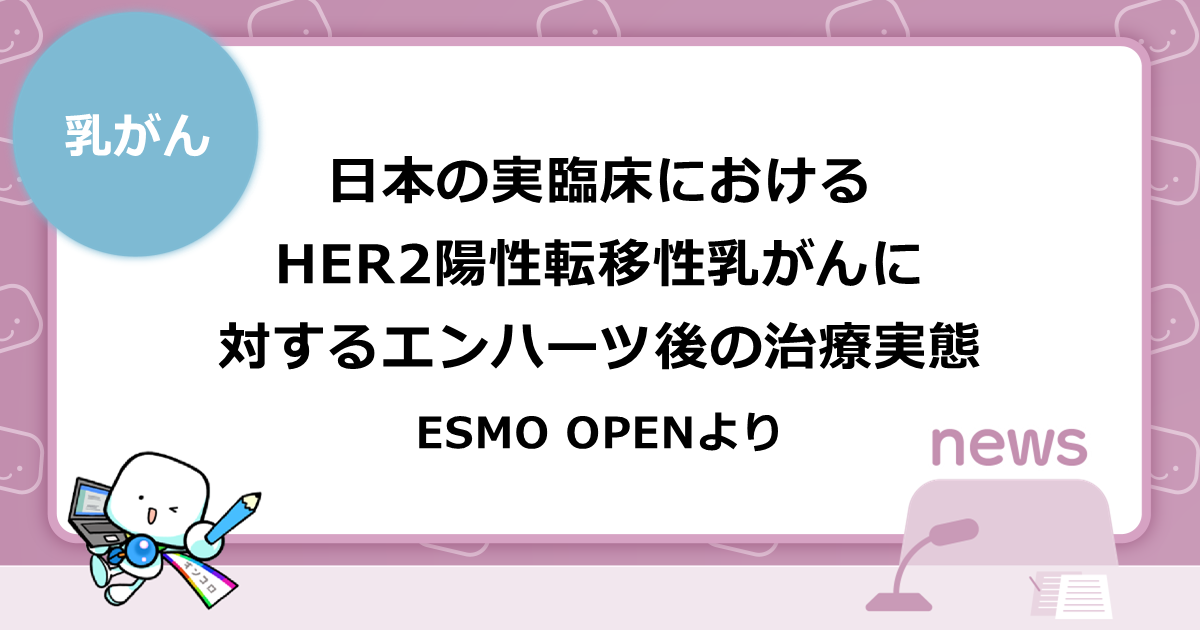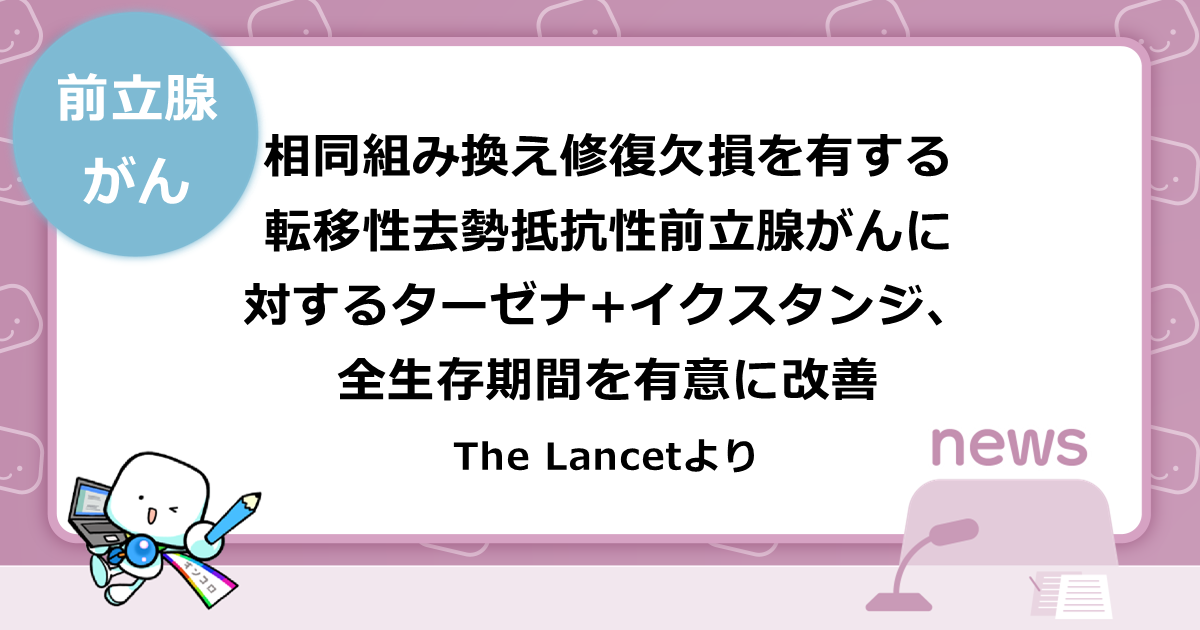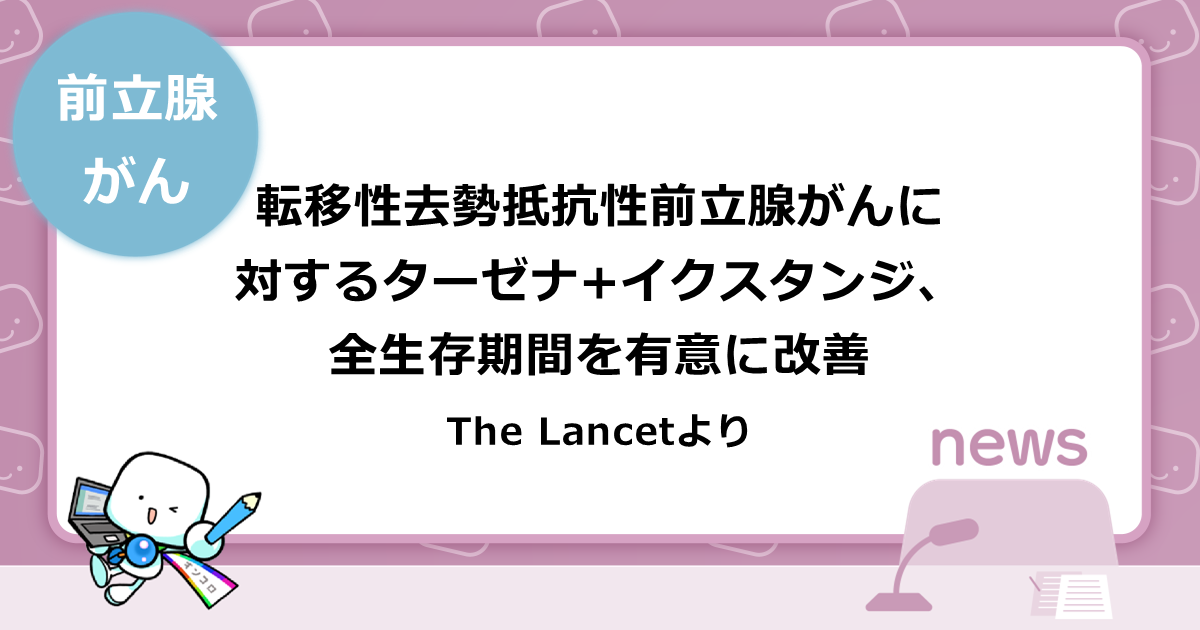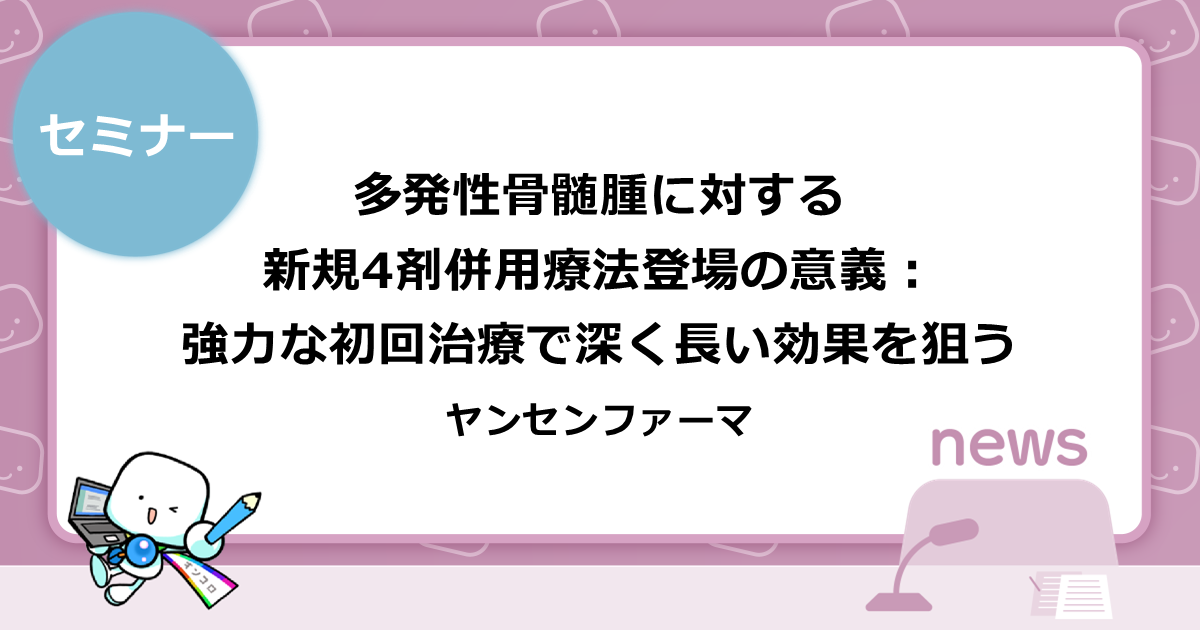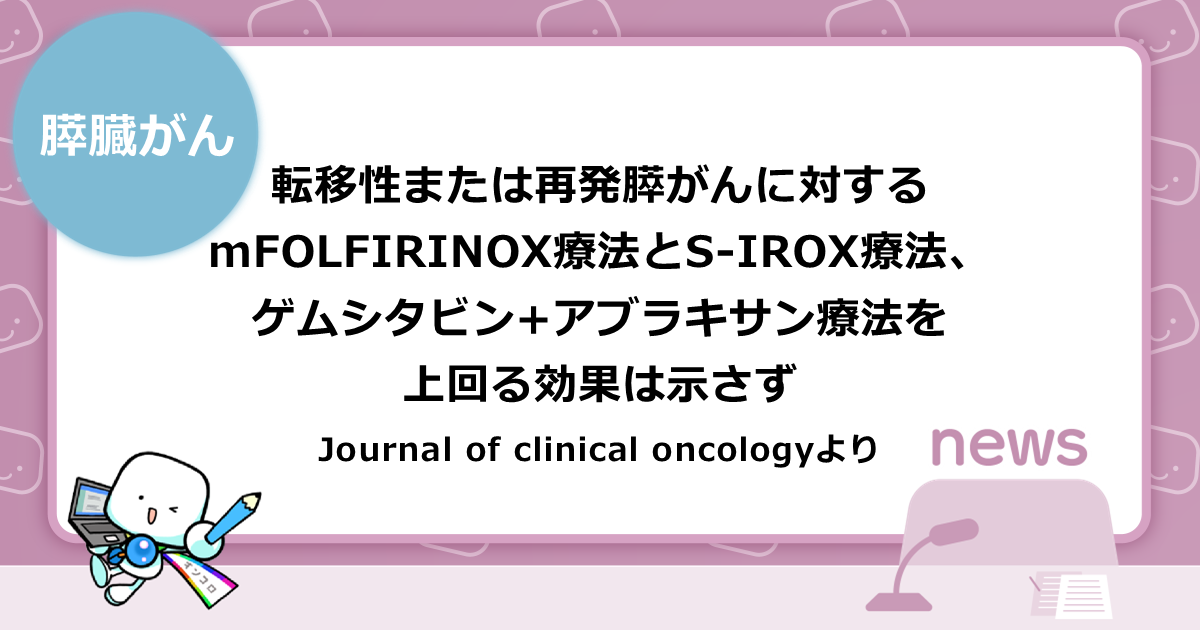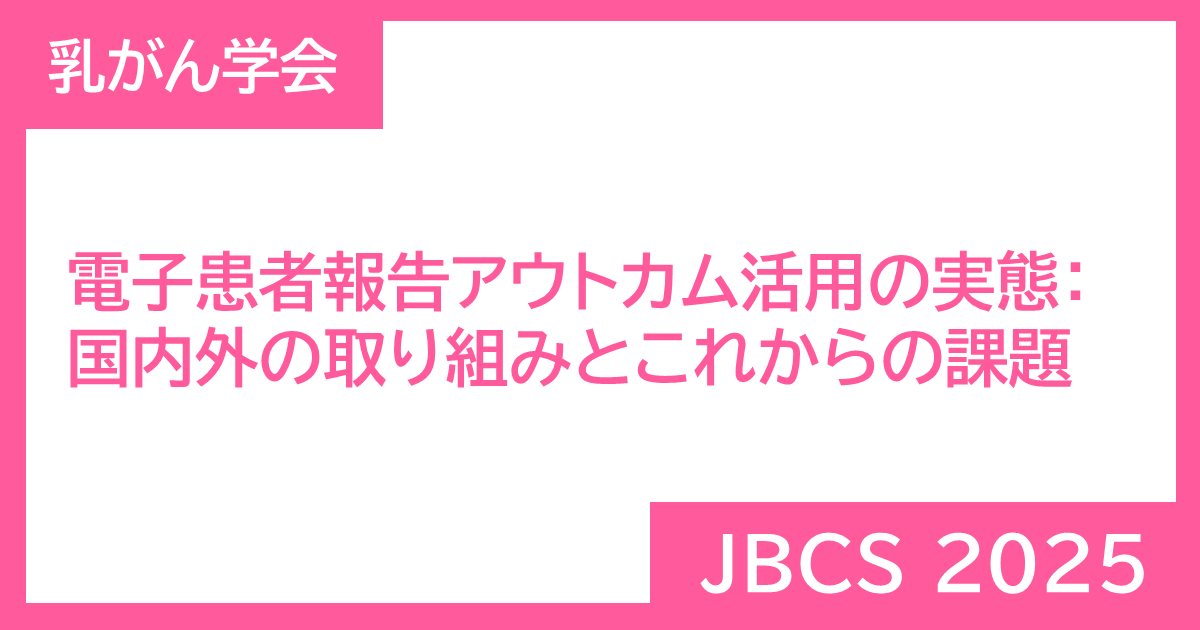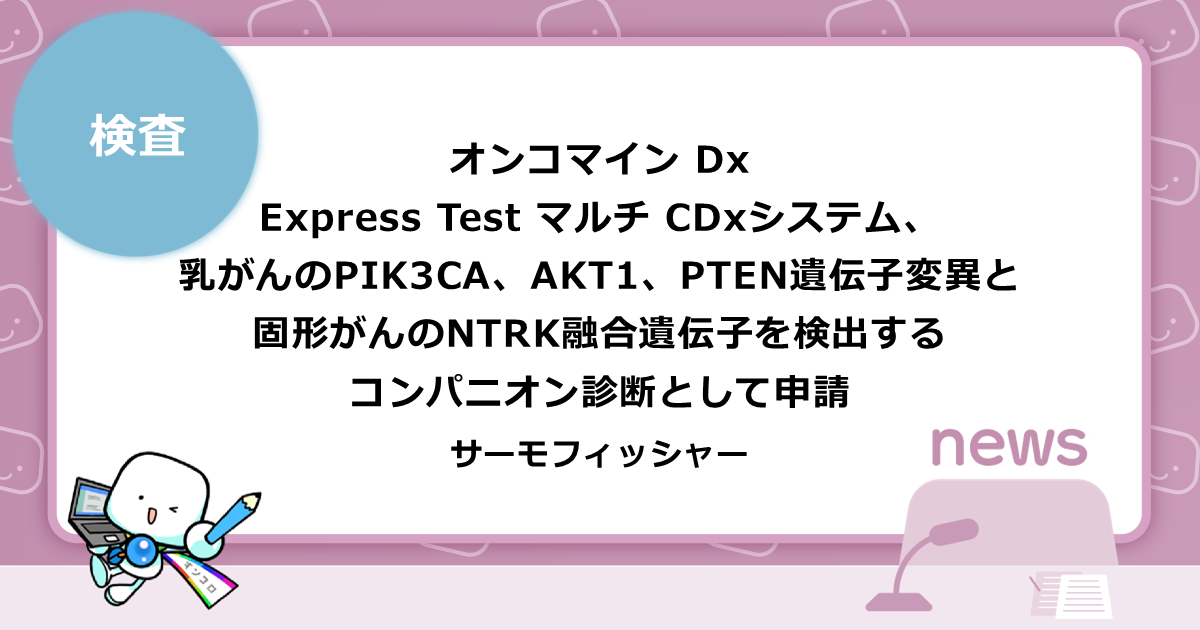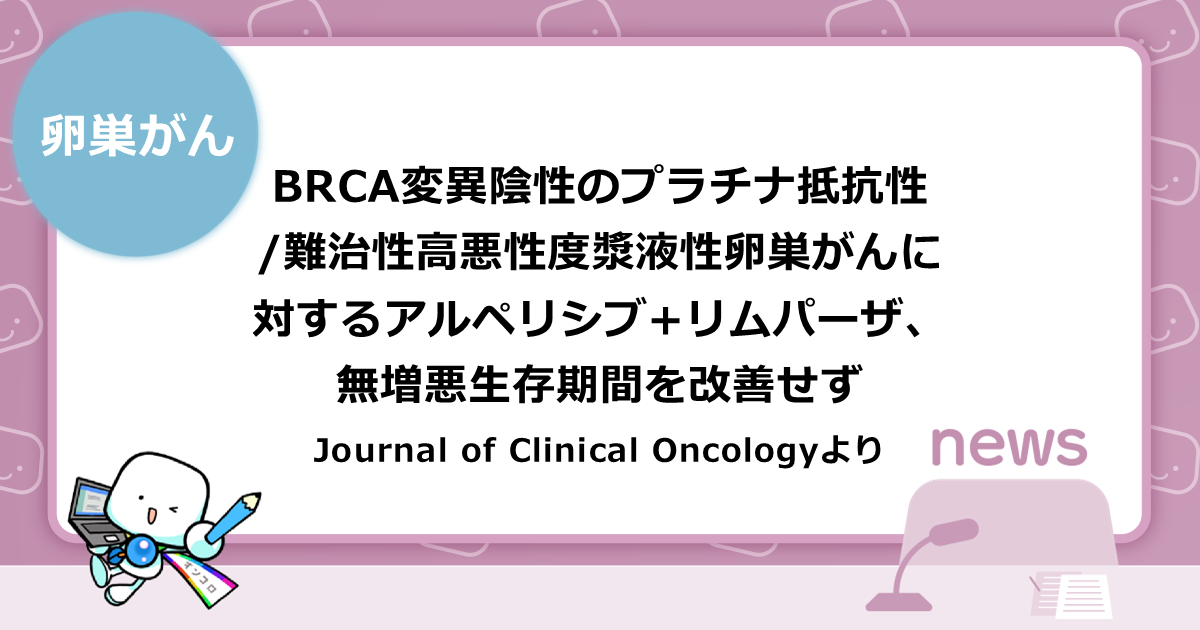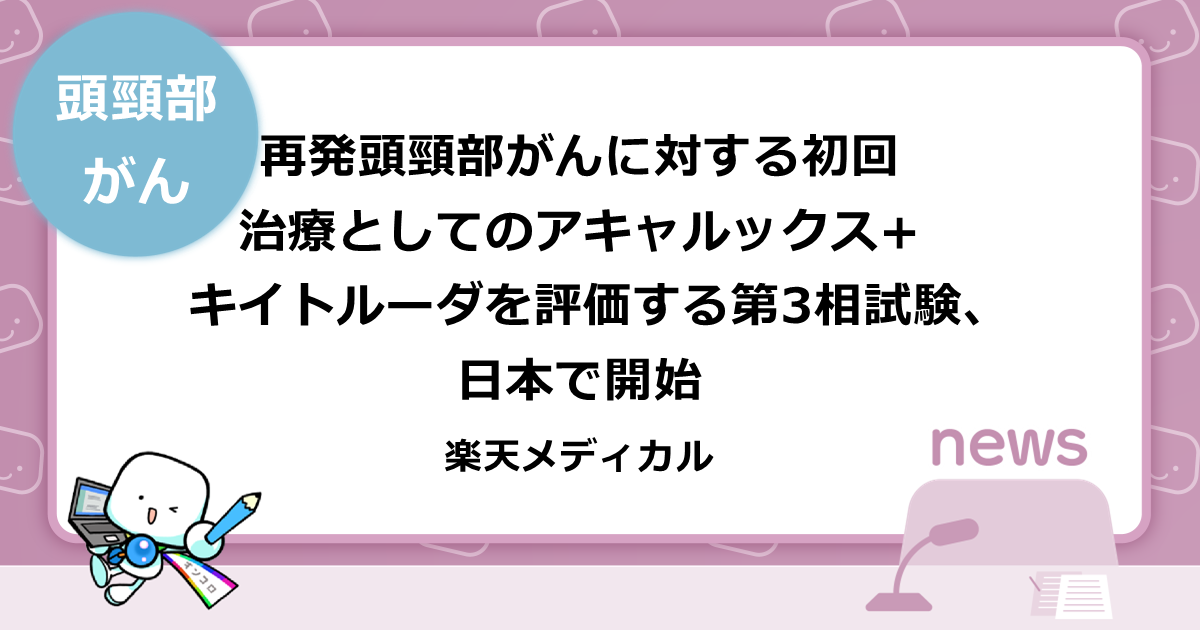小児・AYA世代(15~39歳)ががん治療を行う過程や後遺症で妊孕性が失われてしまうことがあります。しかし適切なタイミングで妊孕性温存を行うことで治療後に子供を授かる可能性を残すことができます。
患者に対し妊孕性について正しく情報提供するため、がん研究会有明病院の職員の方の啓発を目的とした勉強会、「不妊治療技術を用いたがん患者のための妊孕性温存治療-卵巣凍結から子宮移植まで-」が2月8日(木)に開催されました。
[blogcard url="https://oncolo.jp/feature/gcls1"]
[blogcard url="https://oncolo.jp/feature/20180117mk"]
[blogcard url="https://oncolo.jp/feature/20180124mk"]
第一部 生殖補助医療の基礎から応用
講師 婦人科 青木 洋一先生 生殖医療専門医

主に体外受精について講義でした。
まず過去の体外受精の方法ついて「これまではhMG注射を行なっていた。この注射を打つ事で10~20の卵子を得ることができる。
ただ、hMG注射をしすぎると、OHSS(卵巣刺激症候群)という卵巣が腫れた状態になってしまうこともある。また月経に依存してしまうため、すぐに治療が必要ながん患者さんにはいい方法ではない。」と語りました。
現在の体外受精の方法については「今では卵巣自体を凍結する様になった。加えて凍結も技術向上もあった。以前は緩慢凍結法と呼ばれる徐々に凍結させていく方法だった。この方法だと解凍した際にダメになる卵子が多数あった。
その後ガラス加工という方法が出きた。急速に卵子を凍結させるため、解凍しても99%は使用できる。こうした背景があり、抗がん剤治療前に卵巣の凍結をしておくことで、治療後に卵巣を戻すことが可能」と語りました。
胚・卵子凍結と卵巣凍結の違いについては以下の様に述べられました。
「月経に関わらず、潜在的な多数の卵子を一気に凍結できるためがんの治療を遅らせることなく施工できるため、がん治療を受ける女性にとって非常に有効な温存方法となった」
また課題として「がん治療学会の妊孕性ガイドラインでは卵子・卵巣の凍結保存お推奨度はCである。これは技術として新しいため、推奨度が低い。」と挙げられました。
第二部 卵巣凍結技術の開発と臨床
講師 プリンセスバンク代表 香川則子先生

香川先生は京都大学で博士号を取得後加藤レディースクリニックで8年間の研究キャリアを積まれました。加藤レディースクリニック体外受精件数22000/年で世界最大の不妊治療専門施設です。
香川先生からはまずは生殖補助医療技術で可能なことの説明がありました。

その後、表にして卵子保存と卵巣保存の違いについて説明がありました。

「化学療法前の方が採取できる卵子の数は多い。診断が下りるかどうかくらいで卵子保存の相談をした方がいい」とのこと。
「卵子保存は月経開始した女性でないといけない。しかし卵巣保存は小児の時期からも可能。ただ、同意をどう取得するかの問題はある。当事者だけでなく周りの方(パートナー、家族)も一緒に取り組むことが大切」と話されました。
最後に「生殖機能の温存のいつ頃産めるのか、いつ頃産むことが難しくなるのかを、中・高生の時に知っておく事が大切である。日本の卵子/卵巣保存をした患者さんは治療後の未来に希望が持てたと言っていた。」と香川先生の考えを述べられました。
妊孕性のハンドブック
妊孕性温存WGはこの講演会を開催すると同時に、参加者に作成したばかりに妊孕性ハンドブックを配布しました。
今度は、妊娠可能な世代の方ががん治療を受ける際に、ハンドブックを配布していくそうです。

※がん研究会有明病院 妊孕性温存ワーキンググループが作成したハンドブック
 主に体外受精について講義でした。
まず過去の体外受精の方法ついて「これまではhMG注射を行なっていた。この注射を打つ事で10~20の卵子を得ることができる。
ただ、hMG注射をしすぎると、OHSS(卵巣刺激症候群)という卵巣が腫れた状態になってしまうこともある。また月経に依存してしまうため、すぐに治療が必要ながん患者さんにはいい方法ではない。」と語りました。
現在の体外受精の方法については「今では卵巣自体を凍結する様になった。加えて凍結も技術向上もあった。以前は緩慢凍結法と呼ばれる徐々に凍結させていく方法だった。この方法だと解凍した際にダメになる卵子が多数あった。
その後ガラス加工という方法が出きた。急速に卵子を凍結させるため、解凍しても99%は使用できる。こうした背景があり、抗がん剤治療前に卵巣の凍結をしておくことで、治療後に卵巣を戻すことが可能」と語りました。
胚・卵子凍結と卵巣凍結の違いについては以下の様に述べられました。
「月経に関わらず、潜在的な多数の卵子を一気に凍結できるためがんの治療を遅らせることなく施工できるため、がん治療を受ける女性にとって非常に有効な温存方法となった」
また課題として「がん治療学会の妊孕性ガイドラインでは卵子・卵巣の凍結保存お推奨度はCである。これは技術として新しいため、推奨度が低い。」と挙げられました。
主に体外受精について講義でした。
まず過去の体外受精の方法ついて「これまではhMG注射を行なっていた。この注射を打つ事で10~20の卵子を得ることができる。
ただ、hMG注射をしすぎると、OHSS(卵巣刺激症候群)という卵巣が腫れた状態になってしまうこともある。また月経に依存してしまうため、すぐに治療が必要ながん患者さんにはいい方法ではない。」と語りました。
現在の体外受精の方法については「今では卵巣自体を凍結する様になった。加えて凍結も技術向上もあった。以前は緩慢凍結法と呼ばれる徐々に凍結させていく方法だった。この方法だと解凍した際にダメになる卵子が多数あった。
その後ガラス加工という方法が出きた。急速に卵子を凍結させるため、解凍しても99%は使用できる。こうした背景があり、抗がん剤治療前に卵巣の凍結をしておくことで、治療後に卵巣を戻すことが可能」と語りました。
胚・卵子凍結と卵巣凍結の違いについては以下の様に述べられました。
「月経に関わらず、潜在的な多数の卵子を一気に凍結できるためがんの治療を遅らせることなく施工できるため、がん治療を受ける女性にとって非常に有効な温存方法となった」
また課題として「がん治療学会の妊孕性ガイドラインでは卵子・卵巣の凍結保存お推奨度はCである。これは技術として新しいため、推奨度が低い。」と挙げられました。
 香川先生は京都大学で博士号を取得後加藤レディースクリニックで8年間の研究キャリアを積まれました。加藤レディースクリニック体外受精件数22000/年で世界最大の不妊治療専門施設です。
香川先生からはまずは生殖補助医療技術で可能なことの説明がありました。
香川先生は京都大学で博士号を取得後加藤レディースクリニックで8年間の研究キャリアを積まれました。加藤レディースクリニック体外受精件数22000/年で世界最大の不妊治療専門施設です。
香川先生からはまずは生殖補助医療技術で可能なことの説明がありました。
 その後、表にして卵子保存と卵巣保存の違いについて説明がありました。
その後、表にして卵子保存と卵巣保存の違いについて説明がありました。
 「化学療法前の方が採取できる卵子の数は多い。診断が下りるかどうかくらいで卵子保存の相談をした方がいい」とのこと。
「卵子保存は月経開始した女性でないといけない。しかし卵巣保存は小児の時期からも可能。ただ、同意をどう取得するかの問題はある。当事者だけでなく周りの方(パートナー、家族)も一緒に取り組むことが大切」と話されました。
最後に「生殖機能の温存のいつ頃産めるのか、いつ頃産むことが難しくなるのかを、中・高生の時に知っておく事が大切である。日本の卵子/卵巣保存をした患者さんは治療後の未来に希望が持てたと言っていた。」と香川先生の考えを述べられました。
「化学療法前の方が採取できる卵子の数は多い。診断が下りるかどうかくらいで卵子保存の相談をした方がいい」とのこと。
「卵子保存は月経開始した女性でないといけない。しかし卵巣保存は小児の時期からも可能。ただ、同意をどう取得するかの問題はある。当事者だけでなく周りの方(パートナー、家族)も一緒に取り組むことが大切」と話されました。
最後に「生殖機能の温存のいつ頃産めるのか、いつ頃産むことが難しくなるのかを、中・高生の時に知っておく事が大切である。日本の卵子/卵巣保存をした患者さんは治療後の未来に希望が持てたと言っていた。」と香川先生の考えを述べられました。
 ※がん研究会有明病院 妊孕性温存ワーキンググループが作成したハンドブック
※がん研究会有明病院 妊孕性温存ワーキンググループが作成したハンドブック








 病院の詳細検索
病院の詳細検索
 マイページ
マイページ
 オンコロとは
オンコロとは
 メディカル・サポーター
メディカル・サポーター
 Remember Girl’s Power!!
Remember Girl’s Power!!
 0120-974-268
0120-974-268