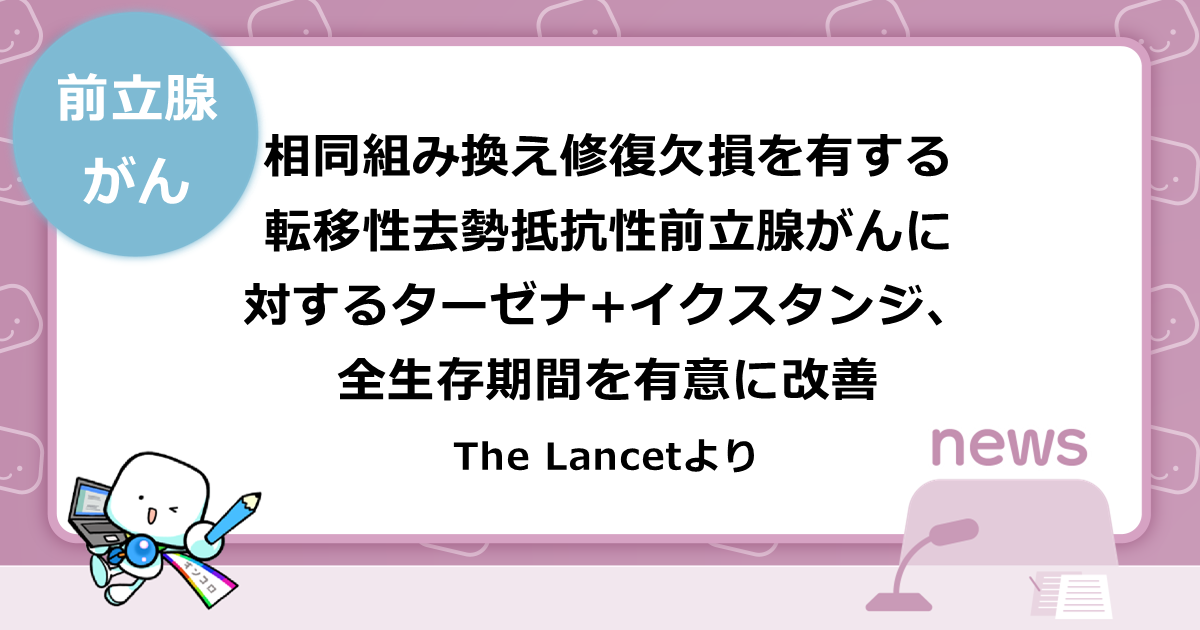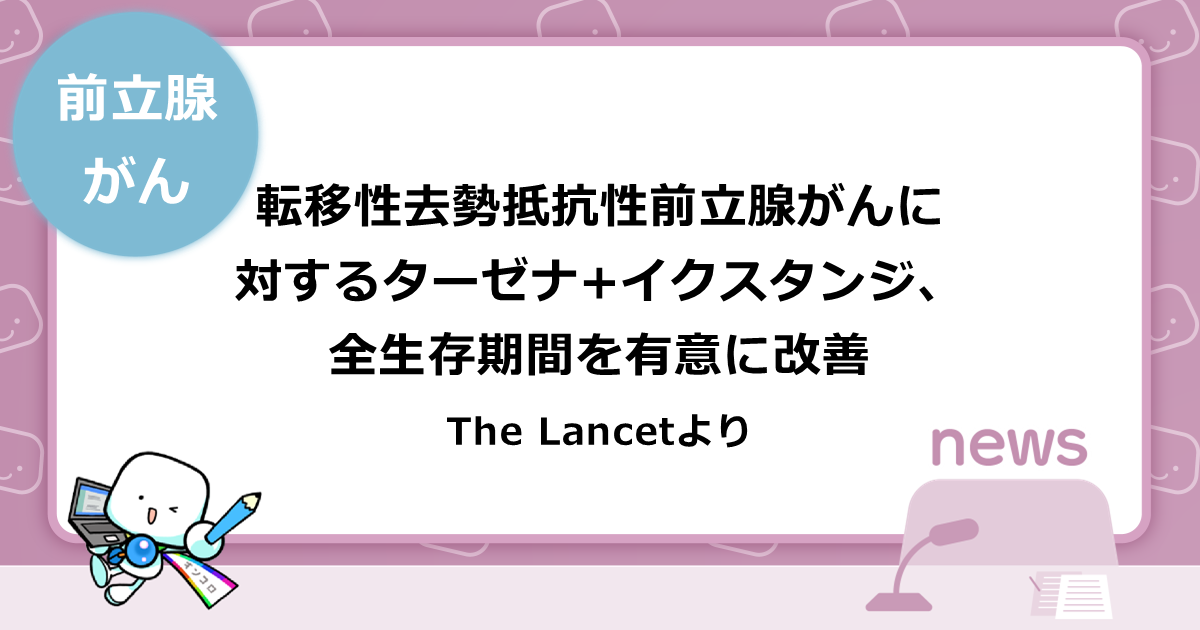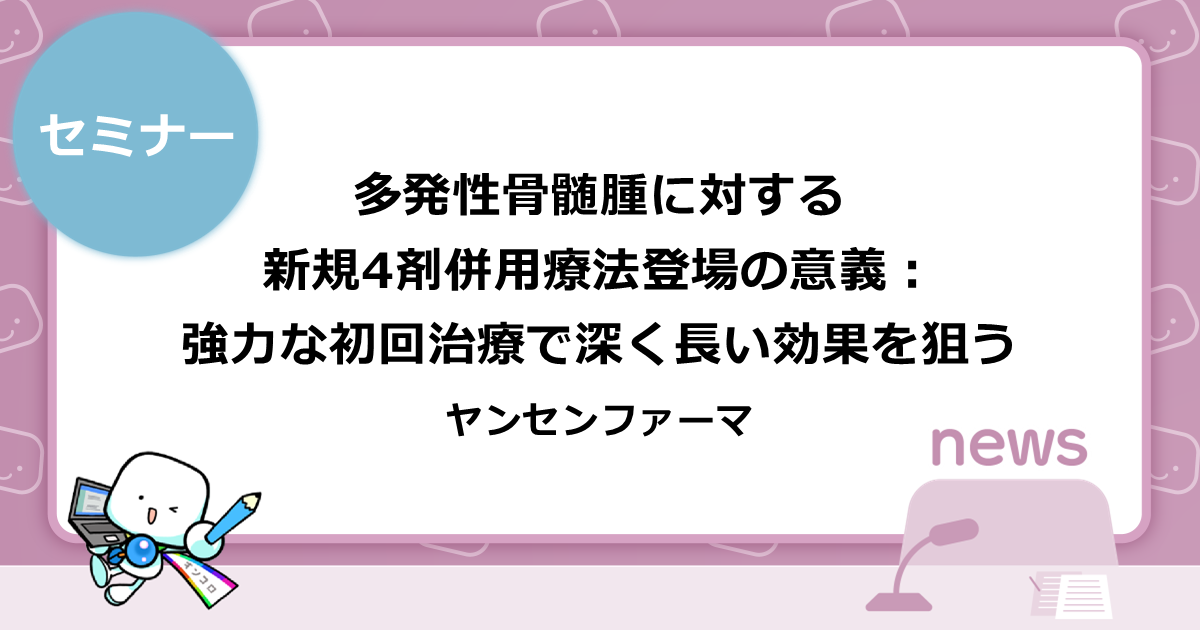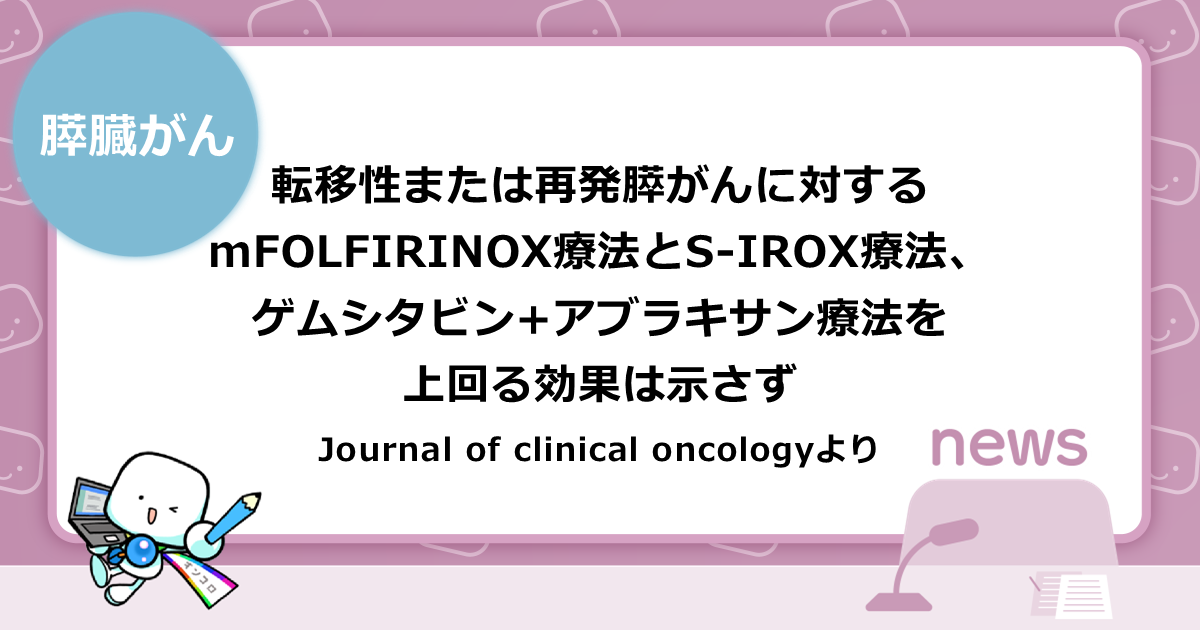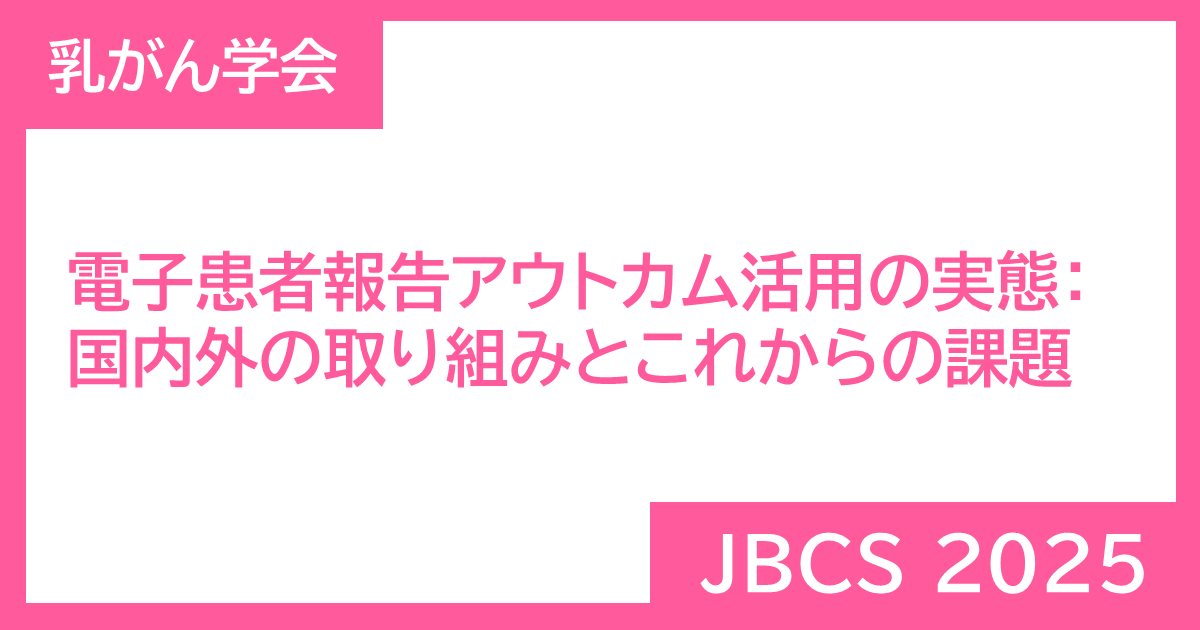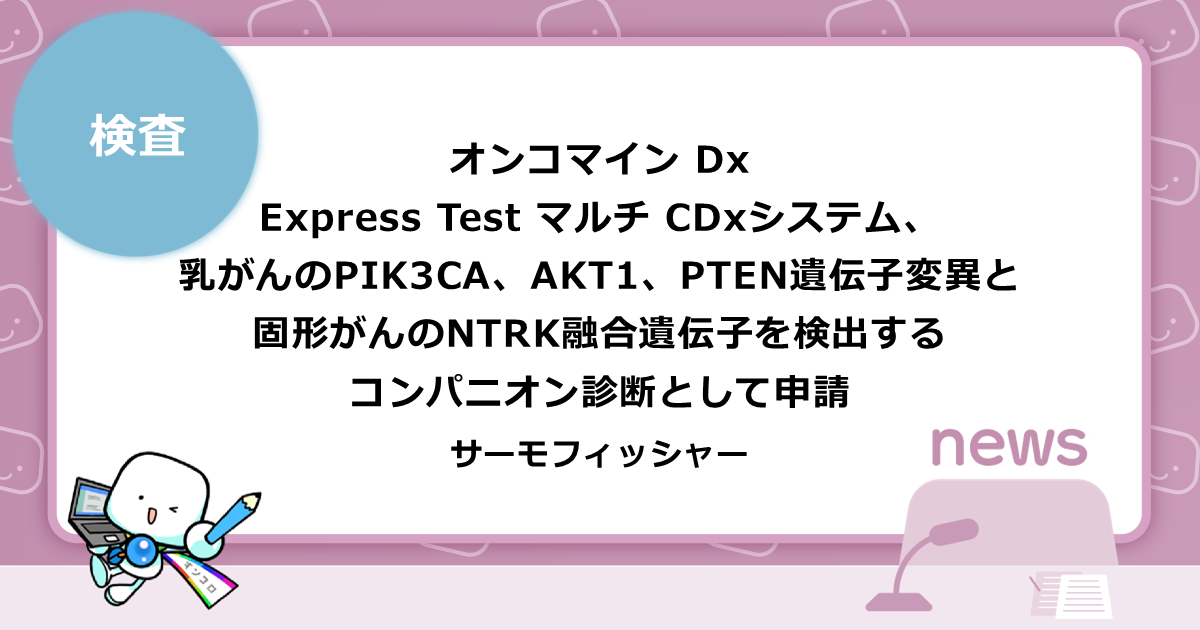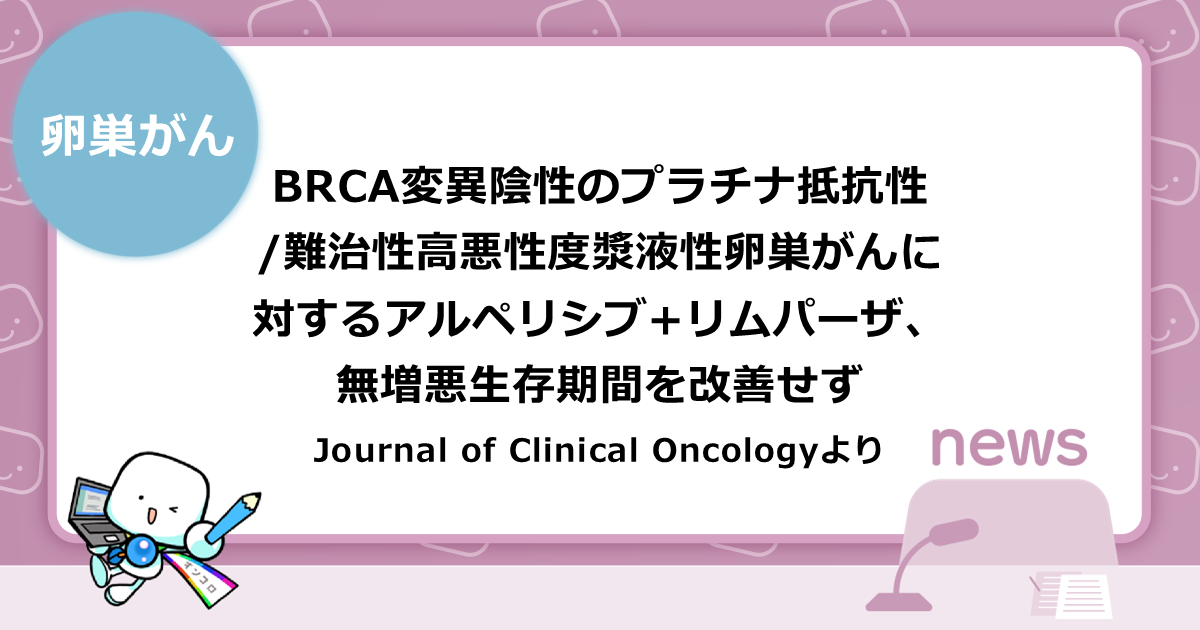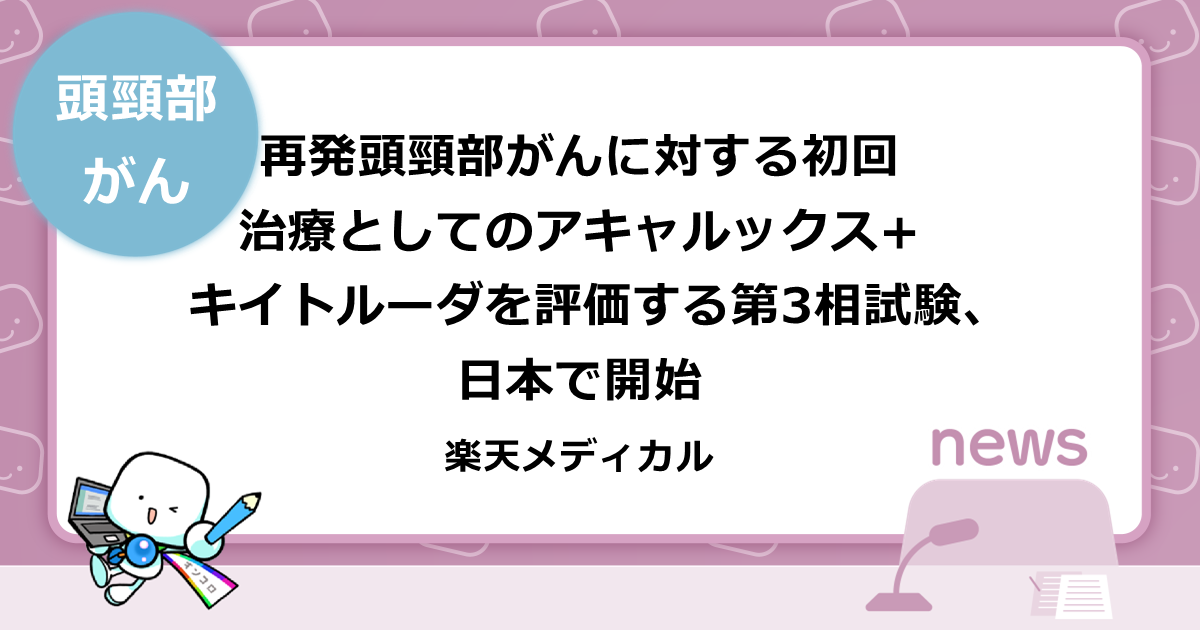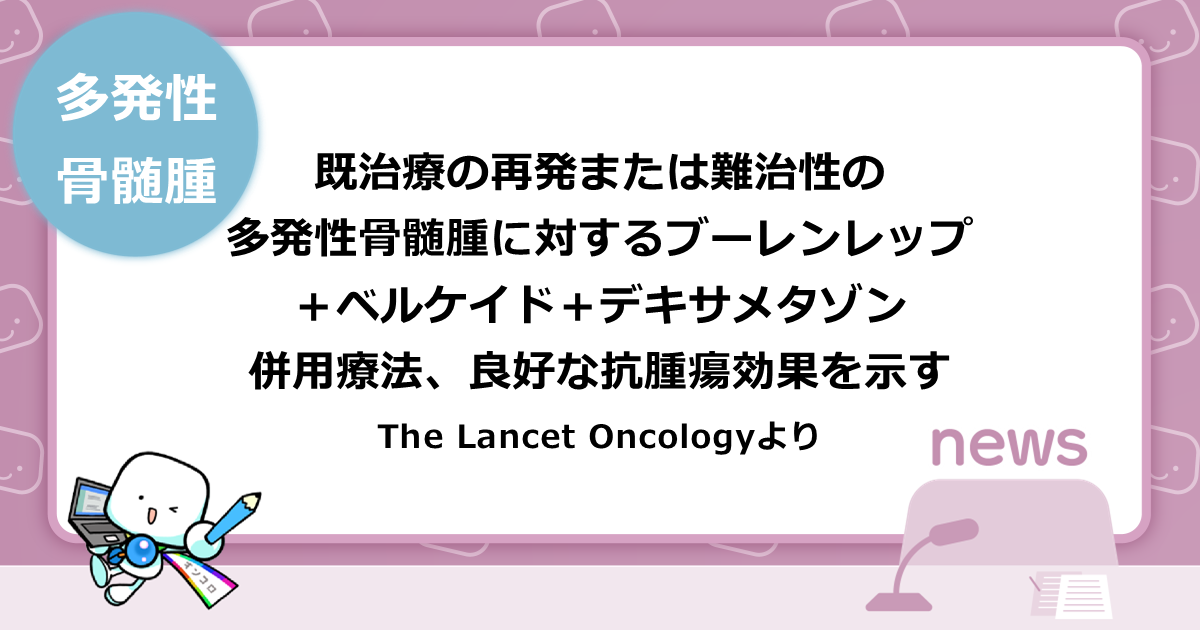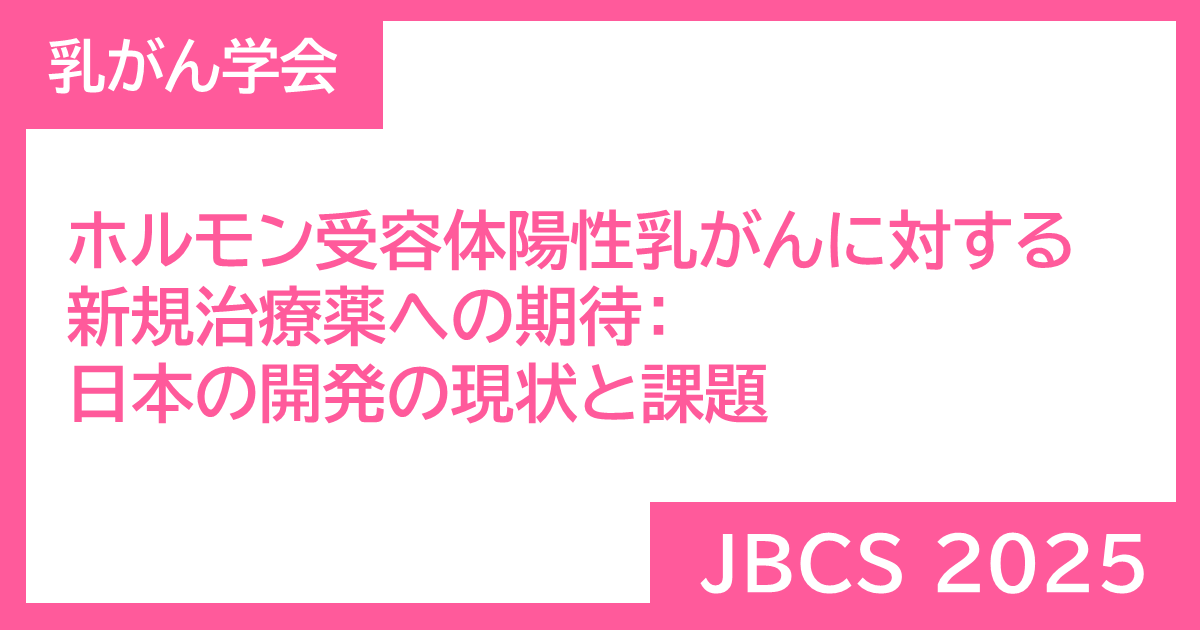目次
プレシジョン・メディシンとは
プレシジョン・メディシン(高精度医療)は、テーラーメード医療や個別化医療の一種となる。がん細胞の遺伝子を次世代シークエンサー(NGS)で解析し、患者ごとにがんの原因となった遺伝子変異を見つけ、その遺伝子変異に効果があるように設計した分子標的薬を使用するといった手法となる。 2016年2月、米国では当時のオバマ大統領が国家プロジェクトである『National Cancer Moonshot(ムーンショット)』イニシアティブを10億ドルを拠出して立ち上げ、その重要な位置づけが、プレシジョン・メディシンとなった。 日本においては、2013年に開始した希少肺がんの遺伝子スクリーニングネットワーク『LC-SCRUM-Japan』が始まり4年の月日が経過し、2017年度よりLC-SCRUM-Japan第二期を迎える。 肺がん(非小細胞肺がん)は、今や希少がんの集合と言われる。EGFR遺伝子変異、ALK遺伝子変異に代表される『がんの引き金になった遺伝子(ドライバーオンコジーン;driver oncogene)の変異』から罹患したがんの集合体であるからだ。 EGFR遺伝子変異(30%)やALK遺伝子変異(5%)に対しそれぞれを標的とした分子標的薬が奏効し、日本で複数の薬剤が承認・上市されている。その他、ROS1遺伝子変異(1~2%)に対しての薬剤も本年8月に承認され、BRAF遺伝子変異(1%)、RET遺伝子変異(1~2%)に対しても複数の薬剤が有望視されている。 一方、プレシジョン・メディシンという言葉が日本中に広まったのは、2016年11月20日にNHKが放映した『NHKスペシャル “がん治療革命”が始まった ~プレシジョン・メディシンの衝撃~』が始まりであると考える。放映後、国立がん研究センターには問い合わせが殺到し、電話がつながりづらい状態に陥った。 その後、プレシジョン・メディシンをテーマにした報道が頻繁にみられるようになった。遺伝子パネル検査の問題は山積み~少しずつ進む体制構築~
プレシジョンメディシンの代名詞である遺伝子パネル検査。 遺伝子パネル検査は、技術向上により多くの医療機関が導入、『研究』または『自由診療』で受けることができるようになった。しかしながら、『研究』であれば患者の自己負担がなくなる一方、研究資金が尽きると継続できなくなる。 近畿大学医学部 ゲノム生物学教室教授である西尾 和人氏は、同大で研究ベースで進める、近大クリニカルシークエンスおよびリキッドバイオプシーから遺伝子パネル検査を行う近大クリニカルシークエンスIIを紹介。「品質が高いことを自負しており、研究として実施しているため患者の負担はなく、施設内検査である我々の検査は2~3週間で結果がでるため、患者さんにとって‘いい検査’である。一方、研究資金を捻出するために、最近、クラウドファンディングにて寄付を募った。本来であれば、コンパニオン診断薬として保険診療下で行うのがベターであるが問題は山積み」と述べた。 なお、西尾氏は、日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会といった日本の主要癌学会合同で作成した『次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス』の作成ワーキンググループ長を務め、2017年10月11日付で第1版が完成した。 一方、国立がん研究センター中央病院 副院長である藤原 康弘氏は「ドラッグラグは無くなったものの、分子標的薬の投与可否を決める検査キット(コンパニオン診断薬)の薬事承認と保険適用の遅れが目立つようになった」と述べた。国レベルでのがん医療推進を検討するためのゲノム医療実現推進協議会が2016年2月より、ゲノム医療等実現推進タスクフォースが同年11月より始まり、がんゲノム医療中核病院などについても議論されている。2017年6月27日に開催されたがんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会では、本コンソーシアムの体制と概要およびがんゲノム医療実用化に向けた工程表が話し合われており、国の体制構築も少しずつ進む。
 がんゲノム医療推進コンソーシアム報告書より
がんゲノム医療推進コンソーシアム報告書より
米国アドボカシーLung Cancer Allianceの逆引き臨床試験検索システム
米国を代表するペイシェントアドボカシーLung Cancer Alliance(ラング・キャンサー・アライアンス;LCA)のJennifer King氏は、科学研究戦略を率いる科学・研究のサイエンティフィックアンドリサーチディレクターとして2015年に参画した。LCAの前には、腫瘍学のヘルスケア学習システムのデータガバナンスディレクター、米国臨床腫瘍学会(ASCO)のConquer Cancer Foundation(意訳:がん克服財団)のアソシエイトディレクターかつサイエンティフィックレビューアーを従事。彼女はメモリアル・スローンケタリングがんセンター、カルフォルニア大学ジョンソン総合がんセンターに研究者として勤務している。 日米のアドボカシーの明確な差の1つに、彼女のようなプロフェッショナルが積極的にかかわる団体の多さがあるといえよう。 そんな彼女が紹介したLCAのシステムは、肺がん臨床試験逆引き検索システム等を備えるWebサイトLungMatchである。 LCAの逆引き臨床試験検索システム
米国のみではなく全世界対応であり、日本も含まれる。ベースが米国臨床試験登録システムClinicaltrials.govとなっているため、すべてを網羅しているわけではないが、筆者が試した限りでは7割程度は日本の臨床試験をカバーしているのではないであろうか。
LCAの逆引き臨床試験検索システム
米国のみではなく全世界対応であり、日本も含まれる。ベースが米国臨床試験登録システムClinicaltrials.govとなっているため、すべてを網羅しているわけではないが、筆者が試した限りでは7割程度は日本の臨床試験をカバーしているのではないであろうか。








 病院の詳細検索
病院の詳細検索
 マイページ
マイページ
 オンコロとは
オンコロとは
 メディカル・サポーター
メディカル・サポーター
 Remember Girl’s Power!!
Remember Girl’s Power!!
 0120-974-268
0120-974-268