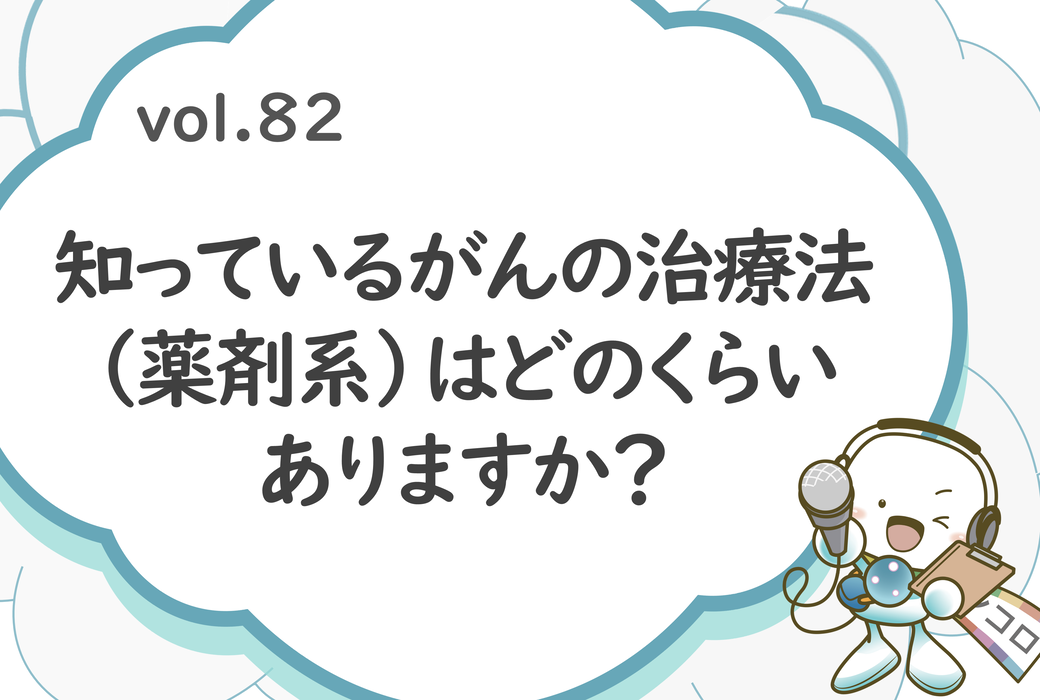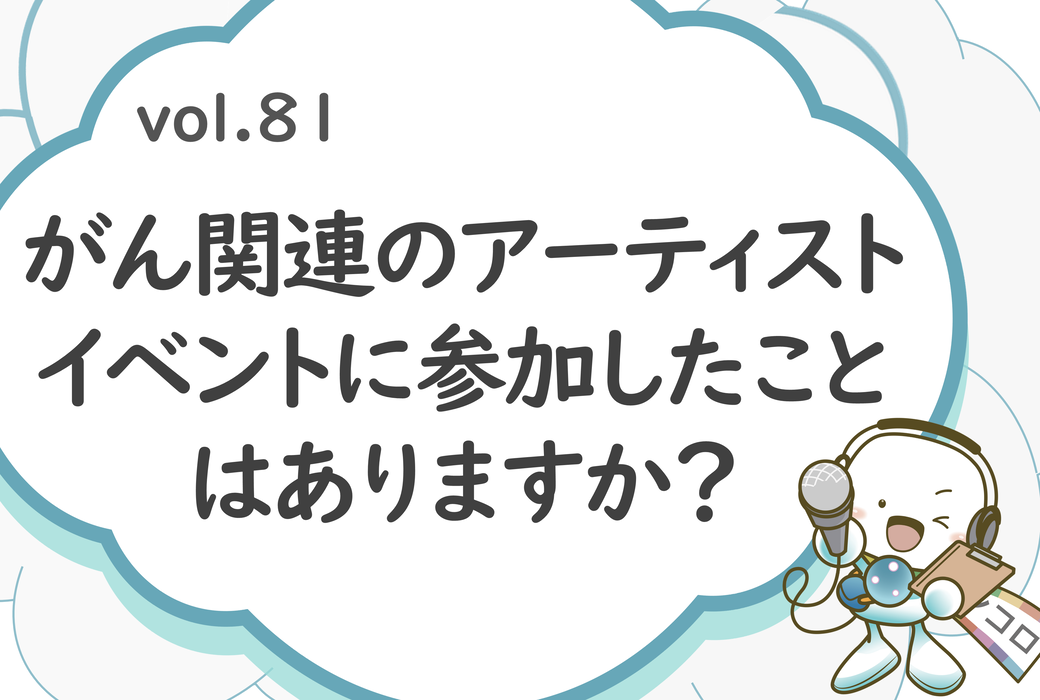6月21日、22日に横浜で緩和医療学会学術大会が開催され、オンコロスタッフの赤星も参加しました。
ここでは、イベントで聴講した内容をご紹介したいと思います。

「緩和ケアの両輪としてのArt&Science―今後に期待すること」
特別講演として、1996年に第1回の日本緩和医療学会学術大会で大会長を務められた柏木哲夫先生がご登壇されました。
先生は、「近代ホスピスの母」と呼ばれるシシリー・ソンダース博士とのやりとりをご紹介されました。ソンダース博士は「もし私ががんの末期になり痛みのために入院した時、私が望むのは痛みが取れるように祈ってくれる牧師でも、経験深い精神科医が悩みに耳を傾けてくれることでもない。
私の痛みの原因をしっかりと診断し、痛みを軽減する薬剤の種類・量・投与間隔・投与法を判断し、それを直ちに実行してくれる医師が来てくれることです」と説かれたそうです。これは、ホスピス医は体をしっかり診る事ができるという事が大切である、という意味です。
先生は、「この出来事は自分の生き方を方向付けた」と仰り、この後、精神科であるにも関わらず、内科や外科でも研鑽を積み、ホスピスを日本に開いたそうです。
次に、言葉についてですが、「緩和医学」は医師が主体となるもので、技術の提供(Science)であり、これは一方性・一方的です。対して「緩和ケア」は、看護師が主体となるものでケアの提供(Art)であり、双方向性で成長につながります。
そして「緩和医療」は、医師と看護師(医療従事者)によるもので、技術とケアの提供で双方向性の概念です。
Cureは治療・治癒・更正・社会性などを意味し、Careは配慮・援助・介護・看護などを意味します。2つの違いは、Cureは技術が必要となるものですが、それが尽きてしまうと限界があります。一方、Careは限界がなく、CureできなくてもCareはできる、と言えます。
苦痛緩和のためのScienceと心のこもった全人的ケアのArt。これは車輪の両輪となるもので、バランスが大切だそうです。今まではScienceの重要性が言われてきたが、Artの部分ももう少し膨らませる必要があるのではないか、と先生は仰いました。
更に、日本にホスピスの問題点として市民の不参加や死の否定もあります。先生は最後に、「患者さん、家族の希望を優先する緩和医療を実践するために、常にScienceとArtのバランスを考え続ける学会である事を今後も期待する」と仰り締めくくりました。
単身者の看取り
“人生会議”については、 オレンジホームケアクリニックの在宅医療専門医である紅谷 浩之先生がご登壇されました。
人生会議とは、厚生労働省が今まで普及を進めてきたアドバンス・ケア・プランニング(ACP)をより馴染みやすい言葉となるように決めた愛称の事です。
もしものときのために、個人が望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のことを意味します。
2018年のガイドライン改定では、「人生最後の段階におけるケア・医療・決定ポイントは家族から家族等(友人)へ」となりました。
以前は「こういう時はこうしてほしい」などの「事前指示」をされてきましたが、これには決めていない・書いていないと決められない、という点がありました。
人生会議では、「結論を急がず、繰り返し話し合う」ことがテーマとされており、「こう思う、〇〇を大切にしたい、〇〇さんに決めてほしい、こんな時わたし(あの人)はどう選ぶか」などが話されます。
単身でも在宅医療・看取りが可能であることなど、病院や人生会議を行えるメンバーとの情報共有が大切だそうです。人生会議はあらたまっての会議ではなく、日々の会話の積み重ねで、多職種や家族と共有しつつ、迷いながら・揺れながらでも伴走していくことだ、と先生は仰いました。
医療ソーシャルワーカーの立場からご登壇された在宅ケアクリニック川岸町の阿部 葉子先生は単身者への支援は、適切な情報提供と説明がその都度本人へなされていることや生き納めの支援として未完の仕事遂行の補助、成年後見人などの制度を紹介するなど社会資源の活用も必要であると仰いました。
がん専門相談員の島根大学医学部附属病院の槇原 貴子先生は単身がん患者さんへの意思決定支援の要点として、単身者はそれぞれ人生の歴史の中で形成された譲れないものや、守りたいものがある。その信念を理解すること。また、本人の価値観や症状の変化による意志の変化などの共有をチームですることである、と仰いました。
がん終末期のリハビリ
まず、緩和ケア医の立場から小牧市民病院 緩和ケア科の渡邊 紘章先生がご登壇されました。余命1か月のがん患者さんのリハビリの現状では、症状増悪のため一時的に入院加療で、在宅復帰を目指したものが多く、マンパワーを考慮しながら最大限の効果を考えます。
緩和ケア病棟から必要に応じて依頼した人は、排泄などベッド周りQOLや車いす移乗、だるさ改善など上っていくリハビリではなく、維持したいリハビリになります。
目的は、患者さんだけではなく家族の視点も重要だそうです。本人の目標達成は自立低下による悲嘆軽減になり、介護負担を減らし自宅療養の可能性を高めます。更に家族の本人らしさ(ボディイメージ)が損なわれるという悲嘆も軽減できます。
また、いつまでやるか、というゴール設定は大切で明確なゴールは設定しやすいと仰いました。(トイレに行ける、外出できる、友人などへ想いを遺す作業の完了)
時にゴールを変更する必要もあり、「進行がん患者さんの身体的自立は必ず損なわれる」という事を忘れず、変化のスピードに医療者は自覚し、衝撃を理解しておくことが大切だそうです。
終了タイミングの判断は「最後までがんばりたい」「リハビリが負担」など価値観が違うため、難しいものとなります。終了タイミングを見極め、本人・ご家族に丁寧に説明することが大切です。
市立三次中央病院 リハビリテーション科の上野 千沙先生は「明日から使える、リハビリの技!~骨転移患者さんの痛みに対して~」という内容で実践的なリハビリ技術を教えて頂きました。
骨転移のある方に避けた方が良い姿勢は、脊椎では体幹回旋、四肢では加重で、痛みが出ないという事は不安軽減になり、自信につながるそうです。
静岡県立静岡がんセンターの田尻 寿子先生は浮腫による苦痛の緩和や※ADL・QOLの視点でのアプローチについてお話頂きました。終末期のリンパ浮腫は、全身性浮腫が合併し、皮膚が脆弱になっています。
浮腫に対するリハビリの目標は、安楽を保つケアでADLとQOLの維持改善を図るものです。スキンケアも重要で、保湿や保護、環境セッティングも必要です。車いすで少し打撲したものが、長期ステロイドによる皮膚脆弱で筋膜まで突出するケースもあるそうです。
とにかく体が重いと訴える場合は、クッションなどを利用したポジショニングが大切で、用手的リンパドレナージュについては、主治医と相談することが大切です。
※ADL…日常生活動作。Activities of Daily Livingの略。食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指します。
緩和ケアにおけるAI、ビッグデータの可能性
このテーマでは名古屋大学大学院 医学系研究科 看護学専攻の佐藤 一樹先生がご登壇されました。
緩和ケア学会ではじめて取り上げられるテーマで、今どの学会でも取り上げられ始めているテーマだそうです。
まず、Alとは人工知能 artificial intelligenceを意味します。明確な定義はありませんが、大量のデータから知識や判断基準などを抽出し、アルゴリズム(問題を解くための計算方法)を発展させます。
AIは4つのレベルに分けられます。レベル1は単純なプログラムで、単純な指示通りに行うものですが、レベル4になると対応パターンが多く、自ら判断基準を検討し、判断できます。(レベル1/温度の変化に応じて機能するエアコンや冷蔵庫 レベル4/ディープランニング(深層学習)を取り入れたAIなど)
自ら学習する「ディープランニング」という画期的な技術は、現在AIを代表する技術で、ディープランニングの登場で、人とAIを比較した試験では人を上回るといった結果が出せるようになりました。
AIが実用化で目指せるものは、医療では画像識別診断の支援、カルテ情報の分析、EBMの収集やゲノム医療、診断・治療支援、予後予測などがあります。
一方、課題として、大量のデータがないと学習できない、良質なデータの不足、ディープランニングはプロセスがブラックボックス(結果の根拠を説明することは現在困難である)、AIをだます技術もある(人には考えられないエラーがある)、などが挙げられます。
また、倫理的な問題として、診断を行う主体は医師であり、AIは医師主体の判断の支援ツールにすぎず、医師が判断の責任を負う必要があります。
佐藤先生は数々の研究データをご紹介されました。その中で、緩和ケアでのAI活用では、予後予測の研究、入院後のせん妄発症リスク、乳がん患者さんの症状予測、救急外来受診リスク、造血幹細胞移植後の死亡リスクなどがあるそうです。
日本でも法整備が進んでおり、電子カルテ、国保データ、がん登録、国立大病院データなどが集められているそうです。厚生労働省はNDBオープンデータという、レセプト情報・特定健診等情報データベースを公開しており、誰でも利用が可能となっております。
また、DPCデータという、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法もあります。これは厚生労働省が収集し管理する情報で病院ごとに公開され利用が可能です。
遺伝性腫瘍の全人的苦痛に緩和ケアは応えられるか?

遺伝性腫瘍診療における多職種連携・精神的サポートの重要性というテーマでは兵庫医科大学 外科学講座 下部消化管外科の冨田 尚裕先生がご登壇されました。
遺伝性腫瘍と診断された方は、「がん」という事と「遺伝」という事、二重の精神負担を背負います。近年ゲノム医療の急速な発展により、かつては「遺伝」がタブー視されていましたが、今は医療者・家族にしっかり見つめあう必要ができてきました。
大多数の遺伝学的検査は保険の適応がない、遺伝医療体制の不十分さ、人手不足なども課題としてあります。そこで、日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)の理事長でもある冨田先生は、学会の取り組みとして人材育成を強化されているそうです。
家族性腫瘍コーディネーターは今秋から称号から資格へと変更予定で、家族性腫瘍カウンセラー(FCC)制度、家族性腫瘍専門医制度の開始、セミナーやガイドラインの作成もされているそうです。
冨田先生は、遺伝性腫瘍は複数診療科の医師やチームで色んな人が共同で当たるべきで、二重の重荷を背負う患者さん、ご家族のサポートが必要でそれには緩和ケアの心が必要だとまとめられました。
日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)ホームページ
遺伝看護専門看護師の立場からは 聖路加国際病院 看護部の大川 恵先生がご登壇されました。
がん遺伝子パネル検査の課題として、向き合う事は簡単な事ではない、と仰いました。体質は治せず、共に生きる必要があります。また、自分だけではなく、血縁者の心配もあります。
最近、一部保険承認されたがん遺伝子パネル検査の目的は、ゲノム変異を明らかにし最適な治療を目指すことです。しかし、遺伝子が分かっても薬と結びつくベストな治療がまだ難しいという問題があります。
遺伝と向き合うスピリチュアルペインとして、意思決定は通常本人が優先されるが、同じくらい血縁者の意思決定は重要です。
「遺伝」の問題は「遺伝子」の問題ではなく、人が人を想う身近な問題であり、遺伝子検査をする患者さんの目的は自分は亡くなっても「家族」の未来のために、と思うところも大きいようです。
様々な課題がありますが、具体的には、治療選択の意思決定が今以上に難しい、複数の医療機関で医療を受ける事で相談窓口を失う、経済的負担が大きくなる、知りたくない遺伝も知ってしまう事がある、などの問題が挙げられました。
認定遺伝カウンセラーの立場からは聖路加国際病院 遺伝診療部の鈴木 美慧先生がご登壇されました。
遺伝情報の特性には「普遍性(変わらない)・共有性(血縁者と一部共有)・将来性(将来予測の可能性)」というキーワードがあります。
遺伝カウンセリングでは、その人らしい選択を一緒に考えるプロセスをするもので、その方に会ってから生涯に続くコミュニケーションだそうです。遺伝子変異の箇所は一生変わりませんが、評価は変わるかもしれません。
寄り添うために、クライアントと対話の時間を作る、十分な情報共有、価値観の共有が大切である、と仰いました。
遺伝医療体制については新潟県立がんセンター新潟病院の三冨 亜希先生がご登壇されました。
患者さんは罪の意識を持っている事も有り、緩和ケア科との連携も大切です。
適切な治療を選べるメリットもとても大きいという事も伝えるべきで、遺伝性がんへの不安から理解不足、正しい情報に目を向けられないというサイクルを断ち切るためにも、患者さんにとって必要な情報の理解を助ける必要があります。
患者さんが納得した意思決定ができるよう、早期からの緩和ケアと協同が必要です。
課題としては、各施設で切れ目のない連携が挙げられます。これは患者さんにとっても安心に繋がります。
セミナーに参加して
誰でも苦しんでいる患者さんに寄り添いたいと思うはずですが、今回「寄り添うだけが緩和ケアではない」というメッセージに、自分はどうすれば自分の能力を使い、患者さんの力になれるかを考え、最善の力を尽くしたいと思いました。もちろん寄り添う心は大切にし、チーム医療のリーダーで、全体を俯瞰する医師のメッセージにもあったようにサポート側だけの熱意を押し付けるのではなく、価値観の共有が重要であると学びました。
問題やリスクも多岐にわたるため、今後さらに、様々なメンバーとチーム内でのコミュニケーションが、一人の患者さんをサポートするうえで必須であると感じました。

 遺伝性腫瘍診療における多職種連携・精神的サポートの重要性というテーマでは兵庫医科大学 外科学講座 下部消化管外科の冨田 尚裕先生がご登壇されました。
遺伝性腫瘍と診断された方は、「がん」という事と「遺伝」という事、二重の精神負担を背負います。近年ゲノム医療の急速な発展により、かつては「遺伝」がタブー視されていましたが、今は医療者・家族にしっかり見つめあう必要ができてきました。
大多数の遺伝学的検査は保険の適応がない、遺伝医療体制の不十分さ、人手不足なども課題としてあります。そこで、日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)の理事長でもある冨田先生は、学会の取り組みとして人材育成を強化されているそうです。
家族性腫瘍コーディネーターは今秋から称号から資格へと変更予定で、家族性腫瘍カウンセラー(FCC)制度、家族性腫瘍専門医制度の開始、セミナーやガイドラインの作成もされているそうです。
冨田先生は、遺伝性腫瘍は複数診療科の医師やチームで色んな人が共同で当たるべきで、二重の重荷を背負う患者さん、ご家族のサポートが必要でそれには緩和ケアの心が必要だとまとめられました。
日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)ホームページ
遺伝看護専門看護師の立場からは 聖路加国際病院 看護部の大川 恵先生がご登壇されました。
がん遺伝子パネル検査の課題として、向き合う事は簡単な事ではない、と仰いました。体質は治せず、共に生きる必要があります。また、自分だけではなく、血縁者の心配もあります。
最近、一部保険承認されたがん遺伝子パネル検査の目的は、ゲノム変異を明らかにし最適な治療を目指すことです。しかし、遺伝子が分かっても薬と結びつくベストな治療がまだ難しいという問題があります。
遺伝と向き合うスピリチュアルペインとして、意思決定は通常本人が優先されるが、同じくらい血縁者の意思決定は重要です。
「遺伝」の問題は「遺伝子」の問題ではなく、人が人を想う身近な問題であり、遺伝子検査をする患者さんの目的は自分は亡くなっても「家族」の未来のために、と思うところも大きいようです。
様々な課題がありますが、具体的には、治療選択の意思決定が今以上に難しい、複数の医療機関で医療を受ける事で相談窓口を失う、経済的負担が大きくなる、知りたくない遺伝も知ってしまう事がある、などの問題が挙げられました。
認定遺伝カウンセラーの立場からは聖路加国際病院 遺伝診療部の鈴木 美慧先生がご登壇されました。
遺伝情報の特性には「普遍性(変わらない)・共有性(血縁者と一部共有)・将来性(将来予測の可能性)」というキーワードがあります。
遺伝カウンセリングでは、その人らしい選択を一緒に考えるプロセスをするもので、その方に会ってから生涯に続くコミュニケーションだそうです。遺伝子変異の箇所は一生変わりませんが、評価は変わるかもしれません。
寄り添うために、クライアントと対話の時間を作る、十分な情報共有、価値観の共有が大切である、と仰いました。
遺伝医療体制については新潟県立がんセンター新潟病院の三冨 亜希先生がご登壇されました。
患者さんは罪の意識を持っている事も有り、緩和ケア科との連携も大切です。
適切な治療を選べるメリットもとても大きいという事も伝えるべきで、遺伝性がんへの不安から理解不足、正しい情報に目を向けられないというサイクルを断ち切るためにも、患者さんにとって必要な情報の理解を助ける必要があります。
患者さんが納得した意思決定ができるよう、早期からの緩和ケアと協同が必要です。
課題としては、各施設で切れ目のない連携が挙げられます。これは患者さんにとっても安心に繋がります。
遺伝性腫瘍診療における多職種連携・精神的サポートの重要性というテーマでは兵庫医科大学 外科学講座 下部消化管外科の冨田 尚裕先生がご登壇されました。
遺伝性腫瘍と診断された方は、「がん」という事と「遺伝」という事、二重の精神負担を背負います。近年ゲノム医療の急速な発展により、かつては「遺伝」がタブー視されていましたが、今は医療者・家族にしっかり見つめあう必要ができてきました。
大多数の遺伝学的検査は保険の適応がない、遺伝医療体制の不十分さ、人手不足なども課題としてあります。そこで、日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)の理事長でもある冨田先生は、学会の取り組みとして人材育成を強化されているそうです。
家族性腫瘍コーディネーターは今秋から称号から資格へと変更予定で、家族性腫瘍カウンセラー(FCC)制度、家族性腫瘍専門医制度の開始、セミナーやガイドラインの作成もされているそうです。
冨田先生は、遺伝性腫瘍は複数診療科の医師やチームで色んな人が共同で当たるべきで、二重の重荷を背負う患者さん、ご家族のサポートが必要でそれには緩和ケアの心が必要だとまとめられました。
日本遺伝性腫瘍学会(旧 日本家族性腫瘍学会)ホームページ
遺伝看護専門看護師の立場からは 聖路加国際病院 看護部の大川 恵先生がご登壇されました。
がん遺伝子パネル検査の課題として、向き合う事は簡単な事ではない、と仰いました。体質は治せず、共に生きる必要があります。また、自分だけではなく、血縁者の心配もあります。
最近、一部保険承認されたがん遺伝子パネル検査の目的は、ゲノム変異を明らかにし最適な治療を目指すことです。しかし、遺伝子が分かっても薬と結びつくベストな治療がまだ難しいという問題があります。
遺伝と向き合うスピリチュアルペインとして、意思決定は通常本人が優先されるが、同じくらい血縁者の意思決定は重要です。
「遺伝」の問題は「遺伝子」の問題ではなく、人が人を想う身近な問題であり、遺伝子検査をする患者さんの目的は自分は亡くなっても「家族」の未来のために、と思うところも大きいようです。
様々な課題がありますが、具体的には、治療選択の意思決定が今以上に難しい、複数の医療機関で医療を受ける事で相談窓口を失う、経済的負担が大きくなる、知りたくない遺伝も知ってしまう事がある、などの問題が挙げられました。
認定遺伝カウンセラーの立場からは聖路加国際病院 遺伝診療部の鈴木 美慧先生がご登壇されました。
遺伝情報の特性には「普遍性(変わらない)・共有性(血縁者と一部共有)・将来性(将来予測の可能性)」というキーワードがあります。
遺伝カウンセリングでは、その人らしい選択を一緒に考えるプロセスをするもので、その方に会ってから生涯に続くコミュニケーションだそうです。遺伝子変異の箇所は一生変わりませんが、評価は変わるかもしれません。
寄り添うために、クライアントと対話の時間を作る、十分な情報共有、価値観の共有が大切である、と仰いました。
遺伝医療体制については新潟県立がんセンター新潟病院の三冨 亜希先生がご登壇されました。
患者さんは罪の意識を持っている事も有り、緩和ケア科との連携も大切です。
適切な治療を選べるメリットもとても大きいという事も伝えるべきで、遺伝性がんへの不安から理解不足、正しい情報に目を向けられないというサイクルを断ち切るためにも、患者さんにとって必要な情報の理解を助ける必要があります。
患者さんが納得した意思決定ができるよう、早期からの緩和ケアと協同が必要です。
課題としては、各施設で切れ目のない連携が挙げられます。これは患者さんにとっても安心に繋がります。








 病院の詳細検索
病院の詳細検索
 マイページ
マイページ
 オンコロとは
オンコロとは
 メディカル・サポーター
メディカル・サポーター
 Remember Girl’s Power!!
Remember Girl’s Power!!
 0120-974-268
0120-974-268